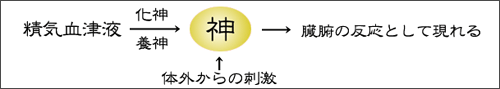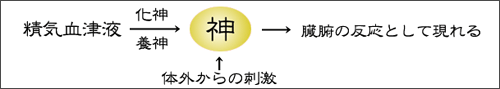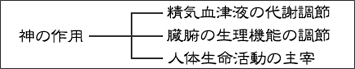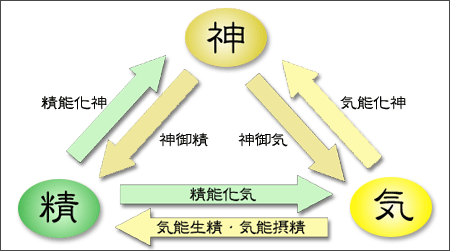神 ( しん / shén / Spirit )
1.定義
広義では人体生命活動の総称とその現れを指す。
狭義では人の精神・思惟活動を指す。
1.1.定義の解説
広義でいう神には精・気・血・津液などの人体を構成する基本物質の代謝をコントロールし、なおかつ各臓腑の生理機能を主宰する働きがある。それゆえ神は人体の生命活動の総称と呼ばれる。また、精・気・血・津液や各臓腑の精気から形成されるため、神はこれら人体を構成する基本物質の盛衰を反映するバロメーターともいうことができる。この場合、神は生理活動や病理変化が人体の外部(眼光・顔色・表情・肌の色艶・呼吸音・話し方・声など)に反映したものとしてとらえ、臨床では「望神」を人の生命力をうかがう重要な指標としている。
狭義の神は、その要素として精神・思惟活動、すなわち心の働きや思考することを指す。神が充実していれば、精神も安定し、物事を冷静に考え決断することができる。
[文献記載] 他文献の神に関する定義など。
[詳細]
神の含意は大変広いが、主なものとして以下の二つが考えられる。
・全ての生理活動・心理活動の主宰である
・生命活動の外在的な現れである(そのうち精神・意識・
思惟活動は狭義の神の範疇に属す)
中医学の神の概念は、古人の生命に対する認識に由来している。
古人は生殖の過程を観察することにより、男女の生殖の
精の結合から、新たな生命が生じることを認識した。これを神の存在であると考えた
1)。
生命の神は、
水穀精微と
津液による絶え間ない滋養により維持され、しだいに発育・成長する
2)。
神の認識が深まるにしたがい、古代哲学における神(すなわち宇宙万物の主宰であるという考え)から類推し、中医学の神は人体生命の主宰であるという概念を確立した。
五臓の機能の協調・精気血津液の貯蔵と輸布・スムーズな情志活動などは、すべて神に統御される。ここから神を人体すべての生理活動と心理活動の主宰とする概念が生まれた。
中医学中の神と古代哲学中の神は、その形成と発展の過程において互いに影響を与えている。ただし、両者は概念や生成の由来に違いがあるため厳格に区別されている。
中医学中の神の産生は物質に依存し、精より生じ
気に養われ生成する。しかし、その概念は精・気などの物質とは明らかな違いがある。
1) 『霊枢・本神篇』"両精相搏謂之神"(両精相搏つこれを神と謂う)
2) 『素問・六節蔵象論篇』"五味人口、蔵於腸胃。味有所蔵、以養五気。気和而生、津液相成、神乃自生"(五味口より入り、腸胃に蔵さる。味に蔵する所ありて、以て五気を養う。気和して生じ、津液相い成りて、神乃ち自ら生ず)
2.神の生成
精・気・血・津液は化神・養神の基本物質である。
神の産生はこれらの精微物質が充実し、関係する臓腑の機能が正常であることが関わっている。また、外部環境からの刺激に対する臓腑の反応とも密接に関わっている。
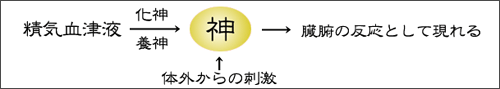
2.1.精気血津液は化神の源
精・気・血・津液は人体を構成する基本物質であるばかりでなく、神生成の物質的な基礎であり、神はこれらの精微物質がなければ存在しない1)2)。[詳細]
神は人体の中に存在し、人体から離れると存在できなくなる
3)。
臓腑・
形体・
官竅の中には精気血津液などの物質が充満している。臓腑の
気の
推動と制御作用のもと、これら
精微物質の新陳代謝により生命活動、すなわち神は生成される。
神とは眼光・顔色・表情・肌の色艶・呼吸音・話し方・声・
脈象などに現れる生命活動の外在表現の総称である。
中医学では神を神・
魂・
魄・
意・
志に分け、それぞれを臓に
帰納し「五神」とした
4)。
五神の物質的な基礎は五臓が蔵する精気である
5)。
五臓の精気が充実していれば、五神は安らかに守られ意識は明晰・
思惟は敏捷・反応は鋭敏で運動はスムーズ・よく眠れ・意志は堅くなる。
五臓の精気が不足すれば、五神を
化生し養うことができず、五神の各種病変が見られるようになる。
精・気・血・津液が充足していれば、臓腑の機能は強健で「
神旺」となる。
逆に、精・気・血・津液が消耗すれば、臓腑の機能は
衰退し「
神衰」となる。
中医診断では望神が最も重要とされ、
聞声・
切脈を結合し、神の盛衰を臓腑の精気の状態を判断する重要な指標とする。これにより、疾病予後の判断をするのに用いる。
2.2.臓腑精気の外部環境への応答
神は自然・社会など外部からの刺激により体内にある臓腑の反応として現れる。[詳細]
なかでも心の作用が最も重要である。心は
神を蔵していることから以下二つの働きを持っている。
・臓腑・肉体・
官竅の働きを主宰・調節する
・心理活動を主る
そのため心は「五臓六腑の大主」と称される。
心を中心とする臓腑は外部からの刺激に対して反応を現す。この反応は以下の二つの面で神の存在を体現する。
・正常な心理活動を保持し、体内の生理活動を主宰・協調している(「
精神内守」)
・外部からの刺激を処理することにより外部環境に順応する
外部からの刺激に対し、心を中心とする各臓腑の働きが協調・整合した結果、正常な精神・意識・
思惟活動が生じる。
また、人の認知活動は以下のように説明される
6)。
・
意:外部からの情報が感覚を通じ心に入り、心の回想活動を経て事物・
表象に対し形成された認識の事を指す
・
志:
憶念を保存していくこと。即ち記憶をもって
事物・表象・認識を累計する過程を指す
・思:「志」を基礎として思索・反復の分析を比較する過程を指す
・慮:「思」の反復を基礎として未来を予想する思惟活動を指す
・智:「意」「志」「思」「慮」を基礎として事物を正確に処理し、行為を支配し事物に対し適当な反応を作り出す措置を指す
外部からの刺激に対する臓腑の反応により様々な情志活動が生まれる
7)。主なものとして七情がある。そして、臓腑の精気の盛衰はこれらの情志の産生に対し決定的な作用を持っている
8)9)。
その他に『霊枢・本蔵篇』では「志意」を挙げ、人の精神活動には自己調節と制御能力があることを指摘している。これらは神の産生と臓腑精気の働きが密接に関係していることを説明している。
1) 『素問・八正神明論篇』"血気者、人之神" (血気なる者は、人の神)
2) 『素問・六節蔵象論』"気和而生、津液相成、神乃自生" (気和して生じ、津液相い成りて、神乃ち自ら生ず)
3) 『荀子・天論』"形具而神生。"(形具なはりて神生ずれば。)
4) 『素問・宣明五気篇』"心蔵神。肺蔵魄。肝蔵魂。脾蔵意。腎蔵志"(心は神を蔵す。肺は魄を蔵す。肝は魂を蔵す。脾は意を蔵す。腎はを蔵す)
5) 『霊枢・本神篇』"肝臓血、血合魂。肝気虚則恐、実則怒。脾蔵営、営舎意。脾気虚則四肢不用、五蔵不安。実則腹脹、経溲不利。心蔵脈、脈舎神。心気虚則悲、実則笑不休。肺蔵気、気舎魄。肺気虚則鼻塞不利、少気。実則喘喝、胸盈仰息。腎蔵精、精舎志"(肝は血を蔵し、血は魂を舎す。肝気虚すれば則も恐れ、実すれば則も怒る。脾は営を蔵し、営は意を舎す。脾気虚すれば則ち四支用いず、五蔵安んぜず。実すれば則ち腹脹し、経溲利せず。心は脈を蔵し、脈は神を舎す。心気虚すれば則ち悲しみ、実すれば則ち笑いて休まず。肺は気を蔵し、気は魄を舎す。肺気虚すれば則ち鼻塞がりて利せず、少気す。実すれば則ち喘喝し、胸盈ちて仰息す。腎は精を蔵し、精は志を舎す)
6) 『霊枢・本神篇』"所以任物者謂之心。心有所憶謂之意。意之所存謂之志。因而存変調之思。因思而遠慕謂之慮。因慮而処物謂之智"(物を任うゆえんの者これを心と謂う。心に憶する所あるこれを意と謂う。意の存する所これを志と謂う。志に因りて変を存するこれを思と謂う。思に因りて遠慕するこれを慮と謂う。慮に因りて物を処すこれを智と謂う)
7) 『素問・陰陽応象大論篇』"人有五蔵化五気、以生喜怒悲憂恐"(人に五蔵ありて五気を化し、以て喜怒悲憂恐を生ず)
8) 『霊枢・本神篇』"心気虚則悲、実則笑不休。"(心気虚すれば則ち悲しみ、実すれば則ち笑いて休まず。)
9) 『素問・調経論篇』"血有余則怒、不足則恐"(血 有余なれば則ち怒り、不足なれば則ち恐る)
3.神の作用
神は生命活動の主宰であり、生命活動全体を指している。神は生命活動に対し有用な調整作用を備えている。
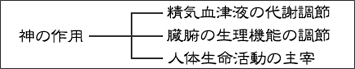
3.1.精気血津液の代謝調節
神は精・気・血・津液などを物質基礎として生成されるが、逆にこれらの物質に対する働きを備える。
神は統制の作用により、精・気・血・津液などの物質が、体内の正常な代謝を調節する働きを担っている1)。
3.2.臓腑の生理機能の調節
臓腑の精気は神を産生する。
逆に神は臓腑の精気を主宰することで、その生理作用を調節する。[詳細]
精神・情志活動は、五臓の精気を物質的な基礎とし生成される。正常な状況下で精神・情志活動は、臓腑の
気の運行が規則正しく協調的であるように制御している。
「五臓蔵五神(五臓は五神を蔵す)」及び「五臓主五志(五臓は五志を主る)」という言葉は生命の
形神統一観を反映している。
神の存在は臓腑の生理機能が正常か否かの反映である。ある種の精神活動は臓腑の生理機能の乱れを調整し、
治病やリハビリの効果をもつ。
3.3.人体生命活動の主宰
神の盛衰は、生命力の盛衰の総合的な体現であり、神の存在は生理活動や心理活動など生命活動の主宰であるといえる2)3)4)。[詳細]
神の統帥と調節の作用は以下の生理活動を統括する。
・
精・
気・
血・
津液の充実と秩序ある運行
・物質
転化とエネルギー転化による代謝の平衡
・臓腑の機能の発揮とその相互の協調
・情志活動の生成と
暢達
・心理状態が安らかで楽しい
・病をしりぞけ長生きをする など
神は生命の存在の根本的な現れであり、形(人体)から神が離れれば則ち形(人体)は亡くなる。形(人体)と神は倶にあり、神を主宰とする。
1) 『類経・摂生類』"雖神由精気而生、然所以統馭精気而為運用之主者、則又在吾心之神。"(神が精気に由而生ずる雖然、精気を統馭し而運用之主と為る所以者、則ち又吾れらが心之神に在り。)
2) 『素問・移精変気論篇』"得神者昌、失神者亡"(神を得る者は昌え、神を失う者は亡ぶ)
3) 『素問・霊蘭秘典論篇』"心者、君主之官也。神明出焉"(心なる者は、君主の官なり。神明焉より出づ)
4) 『素問・宣明五気篇』"心蔵神"(心は神を蔵す)
4.精・気との関係
精・気・神三者の間には相互に依存し利用し合う関係がある。
精は気を化生し、気は精を生むように、精と気の間には相互に化生しあう関係がある。
精気は神を生じ、精気は神を養う。精と気は神の物質基礎であり、また神は精と気を統御する。
したがって、精・気・神の三者は切っても切り離すことができないため人身「三宝」と呼ばれる。
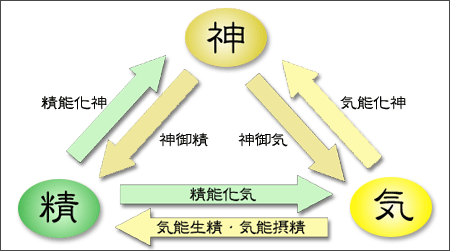
1) 気能生精摂精
気の絶えることのない運行は精の化生を促進している。腎中に蔵される精は、先天の精を基礎とし、後天・水穀の精の絶え間ない充養に頼り始めて充実し盛んとなる。 [詳細]
臓腑の気が充足し機能も正常であって、はじめて水穀の精を運化・吸収することができ、五臓六腑の精は満ちあふれ、腎に流れ込み蔵される。このことから、精の化生は気の状態により左右されることが分かる。
気は精の化生を促進するだけではなく、精を固摂している。固摂されることで精は聚まり充実し、むやみに外泄し損傷することを防いでいる。これは気の固摂作用によるものである。
これらのことから、気虚は精の生成不足あるいは精を固聚できないため精虧・失精などの病証を招く。これらに対し臨床では、補気生精・補気固精などの治療方法を用いることが多い。
2) 精能化気
人体の精は、気の推動作用により気へと化生することができる。 [詳細]
各臓の精は各臓の気を化生し、腎中に蔵される先天の精は元気へ、水穀の精は穀気へと化す。
精は気化生の根源であり、精が充足していれば気は充実し満ちあふれ、各臓腑経絡に分布し、各臓腑経絡の気も充足する。
各臓の精が充足していれば各臓の気も充実し、各臓腑・形体・官竅の生理活動を推動することができる。
したがって、精が充実すれば気は旺盛になり、精が不足すれば気も衰える。臨床において精虚及び失精の患者に気虚の病理表現が多く見られる。
3) 精気化神
精と気は神化生のための物質基礎であり、神は精と気の滋養を受けることではじめて正常に作用を発揮することができる。
[詳細]
精が満ちれば神は明瞭となり、精が不足すれば神は疲弊する。
気が充実すれば神は明瞭となり、気が虚すれば神は衰える。そのため気は「神の母」と呼ばれる。
神は生命活動の主宰であり、精と気、そして血や津液などを含めこれらは全て神の物質基礎である。神と形体は対・相互依存の関係にあり、これら人体の基本物質は人の形体に属す。
神は形体に宿り、形体を離れた神は存在することができない。
4) 神御精気
神は精気を物質基礎とし、逆に神は気や精を統御する1)。 [詳細]
臓腑・形体・官竅の機能活動及び精・気・血など物質の新陳代謝は、すべて神の統御を受けている。
形(形体)は神の住みかであるが、神は形(形体)の主である。神が安定していれば精は固摂され気は通暢である。神が揺れ動き不安定であれば精は失われ気は衰える。
精・気と神の間には対立・統一の関係がある。
中医学の形神統一観は養生と予防及び診断治療・病勢の推測の重要な理論根拠である2)。
1) 『理虚元鑑』"夫心主血而蔵神者也、腎主志而蔵精者也。以先天生成之体質論、則精生気、気生神;以后天運用之主宰論、則神役気、気役精。"(夫れ心は血を主りて神を蔵する者なり、腎は志を主りて精を蔵する者なり。以て先天の体質を論ずるは、則ち精は気を生じ、気は神を生ず;以て後天の運用の主宰を論じれば、則ち神は気を役し、気は精を役す。)
2) 『素問・上古天真論篇』"故能形与神倶、而尽終其天年"(故に能く形と神と倶にして、尽く其の天年を終え)、"独立守神、肌肉若一。故能寿敝天地、無有終時"(独立して神を守り、肌肉一の若し。故に能く寿は天地を敝し、終る時あることなし)