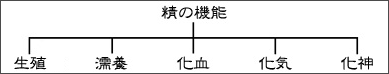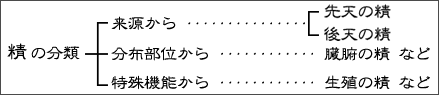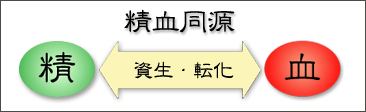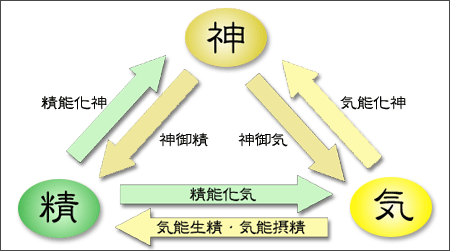精 ( せい / jīng / Essence )
1. 定義
人体の構成や生命活動を維持するための最基本物質。先天の精と後天の精を含む。
1.1. 定義の解説
精はいわば生命の源であり、人体の臓腑経絡などの各組織器官を滋潤・滋養する働きや気・血・神を化生する働きがある。精はその来源により先天の精と後天の精に分類される。先天の精は先天の気(元気)、後天の精は後天の気(宗気・衛気・営気)へ化す。それゆえ精は人体の構成や生命活動を維持するための最も基本となる物質(最基本物質)であると考えられている。
[文献記載] 他文献の精に関する定義など。
[詳細]
精とは、父母より
稟受した生命物質と後天の水穀精微とが融合し形成された一種の
精華物質であり、生命の根源である。また、人体の構成と生命活動維持の最も基本となる物質でもある1) 。精は一般的に液態として臓腑中に貯蔵されるか臓腑間を流動している
2) 3)。
中医学における「精」の概念は、中国古代哲学に含まれる精気学説の影響を受けている。中医学における「精」の概念・理論の確立は、古代哲学における精あるいは水が万物生成の根源であるという思想からの類推に頼るところが大きい。さらに、中医学の「精」の理論は古人の生殖過程の観察と体験、人体が食物から精華物質を吸収する事により生命を維持していることの観察を通じ完全なものとなっていった。
中医学における人体の精とは人類の生命繁殖の根源であり、また人体内部の精華物質を指している。したがって中医学の「精」の概念は、古代哲学の抽象的な精とは異なるものである。
中医学の精には多くの含意がある。本来精とは、生殖の作用を持つ生殖の精のことを指す
4)。
これを狭義の精と称し、中医学における「精」概念の形成の礎としている。これとは別に精華・
精微という意味から発展した、人体内の
血・
津液・
髄及び水穀精微などの精微物質は、すべて広義の精に属す。
ただし、広義の精の生成や機能を細かく分析してみると、精と血・津液・髄の概念間の違いは大きい。そのため、一般的に精の概念には、
先天の精・水穀の精・生殖の精及び臓腑の精のみを含み、血や津液・髄は含めない。
1) 『素問・金匱真言論篇』"夫精者、身之本也"(夫れ精なる者は、身の本なり)
2) 『霊枢・本神篇』"是故五臓主蔵精者也、"(是の故に五臓は精を蔵するを主る者なり)
3) 『素問・経脉別論篇』"食気入胃、散精於肝、"(食気胃に入れば、精を肝に散じ)
4) 『素問・上古天真論篇』"二八腎気盛、天癸至、精気溢写、陰陽和。故能有子"(二八にして腎気盛し、天癸至り、精気溢写し、陰陽和す。故に能く子あり)
2. 精の代謝
精の代謝過程には、精の生成・貯蔵と施泄の三つの段階がある。また、それぞれが相互に関連している。
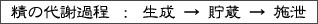
2.1. 精の生成
精には生成の来源の違いから、精には先天の精と後天の精の二種類がある。
1) 先天の精 ( せんてんのせい / xiāntiānzhijīng / Congenital Essence )
[定義] 父母より凛受した精。
[解説] 先天の精とは先天的に父母の生殖により授かった胚胎を構成する物質で、元精・元陰・真陰ともよばれる。先天の精は絶えず「後天の精」の補充を受け、腎において腎精として貯えられる。生命産生・人体の成長発育の源である。
[文献記載] 他文献の先天の精に関する定義など。
[詳細]
先天の精は父母から
稟受した物質であり、胚胎を構成する最初の物質である。古人は生殖過程の観察と体験を通じ、男女の生殖の精の結合により新たな生命体が生まれることを認識した。父母からの遺伝と、新たな生命の誕生は「
精」によるものであり、この精を「先天の精」と呼ぶ
1) 2) 3)。
2) 後天の精 ( こうてんのせい / hòutiānzhijīng / Acquired Essence )
[定義] 水穀より得られる精。水穀の精のこと。
[解説] 後天の精とは後天的に飲食物(水穀)を脾胃が消化吸収することで得られる栄養物質のこと。後天の精は全身の各臓腑組織へと運ばれ、それぞれの生理機能の働きをはたすうえでの基本物質となる。また「後天の精」は絶えず腎に集まり、「先天の精」の働きを補っている。人体を構成する物質のほとんどは後天の精によるものであると言える。
[文献記載] 他文献の後天の精に関する定義など。
[詳細]
後天の精は水穀を
来源とし、「水穀の精」とも呼ばれる。古人は摂取した
水穀の消化・吸収・排泄過程の観察から、人体は摂取した水穀中の
精華物質を吸収することによりはじめて生命を維持できることを認識した。
水穀は脾気の
運化・
昇清により水穀の精へと形を変える。水穀の精は出生後(後天)の生命活動を維持する
精微物質であるため「後天の精」とも呼ばれる。
水穀の精は
津液と混じり合った状態で、脾気の働きにより全身の各臓腑・
形体・
官竅に運ばれる
4)5)。
人体の精のは、先天の精を根本とし、後天の精による絶え間ない補充を受けて、少しずつ充実していく。
したがって、先天の精あるいは後天の精の不足は、いずれも精虚不足の病理変化を引き起こす原因となる。
2.2. 精の貯蔵と施泄
1) 精の貯蔵
人体の精は五臓に分蔵され、なかでも主に腎中に蔵される。[詳細]
先天の精は胎児期には腎に貯蔵され、腎精の主要成分となる。そして、胎児の発育と各臓腑・組織・
形体・
官竅の発達過程において、先天の精の一部は腎以外の臓腑に分蔵される。
後天の精は
水穀に由来し、脾胃により
化生された
精微物質である。脾気の
転輸作用により絶えることなく各臓腑へと運ばれ臓腑の
精と化し、臓腑の生理活動のために用いられる。これと同時にあまった後天の精は腎中に輸送・貯蔵され、腎の蔵する先天の精を
充養する
6)。腎の蔵する精は、先天の精を基礎とし、後天の精の絶え間ない充養を経て徐々に充実していく。
五臓はそれぞれ先天の精・後天の精を蔵しているが、その比率に違いがある。各臓の蔵する精はそれぞれの機能活動を支える物質である。
先天の精は主に腎に蔵され、後天の精の補充を受け生殖の精と化し生殖を行う。そのため、腎は「先天の本」と呼ばれる。
腎の蔵精作用は主に
腎気の
封蔵作用に頼っている。腎精は腎気を
化生し、腎気の封蔵作用は精を腎中に蔵し、むやみに排泄させないようにし、腎精の各種生理機能を発揮させる
7)。
腎気虧虚に陥ると、封蔵機能は低下し
失精の病理変化を招くこととなる。
2) 精の施泄
精の施泄には二種類の形式がある。
① 精は各臓腑に分蔵され、それぞれの臓腑を濡養する。さらに、化気して各臓腑の機能を推動・制御する[詳細]
精は生命活動を維持する最基本物質である。
先天の精は腎に蔵され、後天・水穀の精の補充を受け
腎精と化す。腎精は腎の各種機能の原動力である。
後天の精は脾気の
転輸作用により各臓腑に運ばれ、臓腑の精となる。各臓腑の精と各臓腑の
血・
津液などの物質は相互に
化生し、それぞれの働きから臓腑の生理機能を発揮させている。したがって、臓腑・
形体・
官竅の状態の維持は精の
濡養・滋潤にかかっているといえる。
精は
精華物質であることから、それ自体が各臓腑を
充養するばかりでなく各臓腑の機能活動の物質基礎ともなっている。腎中の先天の精は
元気に化生することを通じ、
三焦を通路とし、全身各臓腑に散布され、各臓腑機能活動を
推動・
発奮し、生命活動の原動力となっている。
このように、精は全身に散布され人体を構成する物質基礎となるだけでなく、各臓腑生理活動に欠かすことのできない精華物質であると言える。
各臓腑の精が不足すれば、その臓腑の生理機能が支えられなくなる。また、
腎精の虧虚は全身の臓腑・組織の生理活動に影響を及ぼす可能性がある。
② 生殖の精と化し、節度ある排泄により生殖をおこなう[詳細]
生殖の精は、
先天の精が
後天の精の援助を受け
化生する。
先天の精に欠損・不足がなく、後天の精による援助を受けられれば腎中に蔵されている
精は充実し、
腎気は満ちあふれ、
天癸も時間通り女子は「二七(14歳)」、男子は「二八(16歳)」の時に至ることとなる。
腎精は天癸の促進作用のもと、生殖の精へと化精し
施泄される
8)。
生殖の精の化生と施泄が規則正しく行われるかは、その他に腎気の
封蔵・肝気の
疏泄及び脾気の
運化の働きが密接に関わっている。
1) 『霊枢・天年篇』"以母為基、以父為楯"(母を以て基と為し、父を以て楯と為す)
2) 『霊枢・決気篇』"両神相搏、合而成形。常先身生、是謂精"(両神相搏わり、合して形を成す。常に身に先んじて生ずるを、是れ精と謂う)
3) 『霊枢・本神篇』:"生之来、謂之精。"(生の来るや、これを精と謂う。)
4) 『素問・厥論篇』"脾主為胃行其津液者也"(脾は胃の為に其の津液を行らしむるを主る者なり)
5) 『素問・玉機真蔵論篇』"言脾為孤蔵、中央土以潅四傍"(脾は孤蔵たりて、中央の土以て四傍に潅ぐと言う)
6) 『素問・上古天真論篇』"腎者主水、受五蔵六府之精而蔵之"(腎は水を主り、五蔵六府の精を受けてこれを蔵す)
7) 『素問六節蔵象論篇』"腎者、主蟄、封蔵之本、精之処也"(腎なる者は、蟄を主り、封蔵の本、精の処なり)
8) 『素問・上古天真論篇』"二八腎気盛、天癸至、精気溢写、陰陽和。故能有子"(二八にして腎気盛し、天癸至り、精気溢写し、陰陽和す。故に能く子あり)
3. 精の機能
精は閉蔵を主り、内にて静かなるものであり、絶え間なく運行する気の性質と対照的であることから、陰の属性を持つ。
精は生殖という重要な作用の他に、濡養・化血・化気・化神などの機能を持つ。
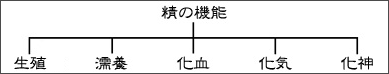
1) 生殖
生殖の精は、先天の精と後天の精が合わさり化生し、生殖の作用を備える。
先天の精は主に腎に蔵され、遺伝の機能を備えている。五臓六腑の精は、いずれも腎に蔵される先天の精を援助し補っている。[詳細]
先天の精・
後天の精は相互に助けあい補いあって
腎精を徐々に充実させる。
腎精より
化生する
腎気も徐々に充実し盛んとなり、人体の
生長と発育を促進・維持する。肉体が一定年齢まで発育・成熟すると「
天癸」が産生され、生殖能力を備えるようになる。
生殖の過程において、父母は生殖の精を通じ生命物質を後代へ遺伝させる。
このことから、腎精は生殖の精という物質を産生するだけでなく、腎気を化生し生殖を促進することが分かる。この後代に与えた生命遺伝物質が、新生命の「先天の精」である。精は生命の根源である。
2) 濡養
精は人体の各臓腑・形体・官竅を滋潤・濡養する。
先天の精と後天の精が充実し盛んであれば、臓腑の精も満たされ、腎精もまた充実し、全身の臓腑・組織・官竅は精の充養が得られ、各種の生理機能は正常に発揮される。[詳細]
先天稟賦の不足あるいは
後天の精の
化生に障害があれば、
腎精は虧虚する。そのため五臓の精も衰え
濡養作用が失われ、臓腑・組織・
官竅は正常な機能が発揮できなくなる。
例えば、
o腎精が損傷すれば、
生長・発育の遅れ、あるいは早老が見られる
o肺精が不足すれば、呼吸障害や皮膚の潤い・つやが無くなるなどの症状が見られる
o肝精が不足すれば、
肝血も不足し筋脈は濡養を失い、痙攣・震えやめまい・ひきつりなどが見られる
腎は蔵精の主な臓腑である。
腎精は
髄を生み、髄が骨を養うことで、骨格は壮健で歯(歯は骨の余り)は堅固となる。また、髄は脳(脳は髄の海・髄海)を養い、脳の生理機能は十分に発揮できるようになる。
腎精の虧虚は、髄を生むことができず、骨格は栄養を失い歯牙は揺れ動き抜け落ちる。また、髄海の不足により、眩暈や精神疲労・知力の低下を招く。
3) 化血
精は血に転化(化血)することができる。精は血生成の来源の一つである。[詳細]
また、腎精が充実していれば、肝を養うことができ
血も充実する
1)。ゆえに、
精が充足すれば血も旺盛となり、精の虧虚は
血虚を招く。
精の化血にはもう一つの意義がある。
精は
精微な生命物質であり、単独で臓腑中に存在することもできるが、絶え間なく血中に融合している。
例えば、心精は心血中に融合していることが多く、肝精は
肝血に融合しその
濡養作用を発揮している。
4) 化気
精は気へと化生(化気)することができる2)。
先天の精は先天の気(元気)へと化生することができ、水穀の精は穀気へと化生することができる。穀気は更に肺の吸入する自然界の清気と交わり一身の気となる。気は絶え間なく人体の新陳代謝を推動・制御し、生命活動を維持している。
したがって、精は生命の根源であり、人体を構成する最基本物質であるといえる。[詳細]
臓腑中に分蔵された先・
後天の精は、臓腑の精と呼ばれる。一身の気は臓腑中に分布し臓腑の気の一部となる。
先・後天の精が充実し盛んとなれば、そこから
化生する一身の気も当然充足する。
各臓腑の精が充足すれば、そこから化生する臓腑の気も自然と満ちあふれてくる。
各臓腑の気はそれぞれの臓腑の機能を
推動・制御し、他臓腑の機能と協調し、共同で生命過程を維持している。
精は
気を化生し、気は肉体の保護・外邪の侵入を防御する能力を持つ。精が充実していれば正気は旺盛となり、病に対する抵抗力は高まり
病邪の侵襲を受けにくくなる
3)。
つまり、臓腑の精が充実していれば、腎精も充実し
化気も十分となる。気が充実していれば人体の生命活動は旺盛で健康であり生殖能力も正常、外邪の侵襲を防ぎ病を退けることができる。
臓腑の精が不足すれば、腎精は衰弱し化気は低下する。気が不足していれば
病邪に対する抵抗力や生殖能力は低下し、全ての生命活動に対し不利な状況に陥る。
5) 化神
精は神に化す(化神)ことができる。 精は神化生の物質基礎である。[詳細]
神は生命活動の外面に現れる総合的な表現である。そして、神の産生に
精は不可欠である
4)。精が集まり、はじめて完全な神となる。これは生命が存在するための根本的な条件である
5)。
反対に、精が不足すれば神は疲弊し、精が亡くなれば神は散じ生命活動は停止する。
1) 『張氏医通・諸血門』"精不泄、帰精于肝而化清血。"(精不泄なれば、精は肝へ帰りて清血と化す。)
2) 『素問・陰陽応象大論篇』"精化為気"(精は化して気となり)
3) 『素問・金匱真言論篇』"故蔵於精者、春不病温"(故に精を蔵する者は、春に温を病まず)
4) 『霊枢・平人絶穀篇』"神者、水穀之精気也"(神なる者は、水穀の精気なり)
5) 『素問・刺法論篇・遺篇』"精気不散、神守不分"(精気散せず、神守分かたれず)
4. 精の分類
精はその来源により、先天の精と後天の精とに分類できる。
その分布する部位により各臓腑の精や、特殊な機能を有する生殖の精などがある。
精(一身の精)は先天の精と後天の精が融合し生成され、各臓腑に分蔵されれば臓腑の精となり、生殖のために施泄されるものは生殖の精となる。
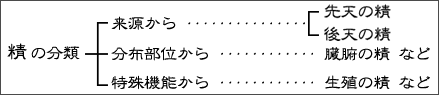
1) 先天の精と後天の精
人体の精は、その生成の来源により先天の精と後天の精に分類できる。[詳細]
先天の精は、父母より
稟受する精である。父母の生殖の精は、胚胎を構成する原始物質であり、生命誕生の根源である。
後天の精は
水穀に由来する。脾胃などの臓腑の働きにより吸収された水穀の
精華であり、生命活動を維持する重要な物質である。
先天の精を基礎とし、後天の精により補充をする。両者の互いに助け・補う関係により、一身の精の生成は行われ、精は徐々に充実し盛んになっていく。
2) 臓腑の精
臓腑中に分蔵された精を臓腑の精と呼ぶ。[詳細]
先天の精は胚胎を形成する。胚胎の発育過程において、先天の精は五臓六腑の組織構造及び生理活動の最も基本となる物質となっている。
さらに、先天の精は
元気を
化生し、各臓腑の機能活動を促進している。したがって、各臓腑の精には先天の精の成分が含まれている。
一方で、
後天の精は脾気の
転輸により各臓腑へ注ぎ込まれ、臓腑の精の主要成分となっている。
臓腑の精は各臓腑を滋潤・
濡養するだけでなく、臓腑の気を
化生し、臓腑の生理活動を
推動・制御している。
3) 生殖の精
生殖の精は腎精に由来し、先天の精が後天の精の援助を受け化生され、生殖の作用を持つ。[詳細]
人々は生殖活動の過程において、生殖の精の交配を通じ生命物質を子に遺伝させている。
男女双方の生殖の精が結合し胚胎を形成し、新たな生命体を誕生させる。
5. 気・血・神との関係
5.1. 精と血の関係
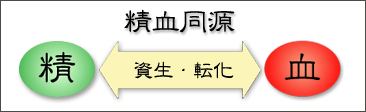
1) 精血同源
精と血はいずれも水穀の精微より化生し充養される物質であり、来源は共通である。両者は相互に補い・転化する関係にあり、どちらも濡養と化神などの作用を備えている。精と血のこの種の関係(来源が同じで、相互に補い転化する関係)を「精血同源」と呼ぶ。[詳細]
精は
血化生の基本物質のひとつである。
先・
後天の精は臓腑中に分蔵され、臓腑の精となる。臓腑の精は血に流入し血となる。
例えば、
o肝精・心精はそれぞれ
肝血・心血に流入し、肝血・心血となる
o脾精は脾が
運化・吸収した水穀の精である。その中の精専部分が
営気と化し、清稀部分が
津液と化し、営気と津液は脈に入り血と化す
o
腎精は肝腎の
気の
推動作用のもと、肝に入り血と化す
このように、先天の精・後天の精が充足していれば、臓腑の精は盛んであり、全身の血も充実する。
腎は蔵精の臓であるため、腎精化血の意義はとりわけ重要である。腎精は血と化し、頭髪を栄養するので「髪は腎の
外華」または「髪は
血余」と称される。したがって、腎精の
虧耗は
血虚病証を引き起こし、同時に頭髪がやせつやが無くなり抜け落ちるなどの症状が出現する。
血は後天・水穀の精を主な
来源とし、腎精は後天・水穀の精に頼り絶え間なく
充養されている。血も精へ化すことができるため絶えず腎の蔵する精を補い滋養し腎精を充実させている。ゆえに、血が充実していれば精は充足し、血が不足すれば精も虧虚となる。
腎の蔵精・肝の
蔵血・精能生血・血可化精など、この種の精血間の相互に補い・
転化する関係を「精血同源」または「肝腎同源」と呼ぶ。
5.2.精・気・神の関係
精・気・神三者の間には相互に依存し利用し合う関係がある。
精は気を化生し、気は精を生むように、精と気の間には相互に化生しあう関係がある。
精気は神を生じ、精気は神を養う。精と気は神の物質基礎であり、また神は精と気を統御する。
したがって、精・気・神の三者は切っても切り離すことができないため人身「三宝」と呼ばれる。
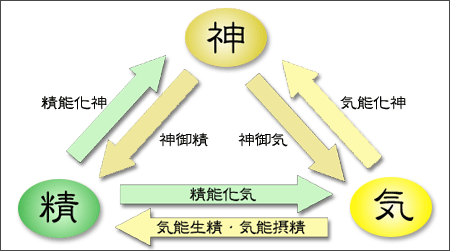
1) 気能生精摂精
気の絶えることのない運行は精の化生を促進している。腎中に蔵される精は、先天の精を基礎とし、後天・水穀の精の絶え間ない充養に頼り始めて充実し盛んとなる。 [詳細]
臓腑の気が充足し機能も正常であって、はじめて水穀の精を
運化・吸収することができ、五臓六腑の精は満ちあふれ、腎に流れ込み蔵される。このことから、
精の
化生は気の状態により左右されることが分かる。
気は精の化生を促進するだけではなく、精を
固摂している。固摂されることで精は
聚まり充実し、むやみに
外泄し損傷することを防いでいる。これは気の
固摂作用によるものである。
これらのことから、
気虚は精の生成不足あるいは精を
固聚できないため
精虧・
失精などの病証を招く。これらに対し臨床では、
補気生精・
補気固精などの治療方法を用いることが多い。
2) 精能化気
人体の精は、気の推動作用により気へと化生することができる。 [詳細]
各臓の精は各臓の気を
化生し、腎中に蔵される
先天の精は
元気へ、水穀の精は穀気へと化す。
精は
気化生の根源であり、精が充足していれば気は充実し満ちあふれ、各臓腑経絡に分布し、各臓腑経絡の気も充足する。
各臓の精が充足していれば各臓の気も充実し、各臓腑・
形体・
官竅の生理活動を
推動することができる。
したがって、精が充実すれば気は旺盛になり、精が不足すれば気も衰える。臨床において精虚及び
失精の患者に
気虚の病理表現が多く見られる。
3) 精気化神
精と気は神化生のための物質基礎であり、神は精と気の滋養を受けることではじめて正常に作用を発揮することができる。
[詳細]
精が満ちれば
神は明瞭となり、精が不足すれば神は疲弊する。
気が充実すれば神は明瞭となり、気が虚すれば神は衰える。そのため気は「神の母」と呼ばれる。
神は生命活動の主宰であり、精と気、そして
血や
津液などを含めこれらは全て神の物質基礎である。神と形体は対・相互依存の関係にあり、これら人体の基本物質は人の
形体に属す。
神は形体に宿り、形体を離れた神は存在することができない。
4) 神御精気
神は精気を物質基礎とし、逆に神は気や精を統御する1)。 [詳細]
臓腑・
形体・
官竅の機能活動及び
精・
気・
血など物質の新陳代謝は、すべて
神の統御を受けている。
形(形体)は神の住みかであるが、神は形(形体)の主である。神が安定していれば精は
固摂され気は通暢である。神が揺れ動き不安定であれば精は失われ気は衰える。
精・気と神の間には対立・統一の関係がある。
中医学の形神統一観は養生と予防及び診断治療・病勢の推測の重要な理論根拠である2)。
1) 『理虚元鑑』"夫心主血而蔵神者也、腎主志而蔵精者也。以先天生成之体質論、則精生気、気生神;以后天運用之主宰論、則神役気、気役精。"(夫れ心は血を主りて神を蔵する者なり、腎は志を主りて精を蔵する者なり。以て先天の体質を論ずるは、則ち精は気を生じ、気は神を生ず;以て後天の運用の主宰を論じれば、則ち神は気を役し、気は精を役す。)
2) 『素問・上古天真論篇』"故能形与神倶、而尽終其天年"(故に能く形と神と倶にして、尽く其の天年を終え)、"独立守神、肌肉若一。故能寿敝天地、無有終時"(独立して神を守り、肌肉一の若し。故に能く寿は天地を敝し、終る時あることなし)
![]()