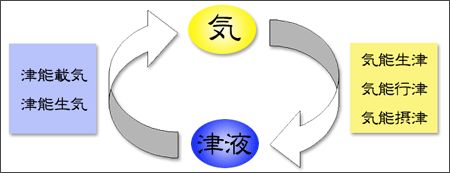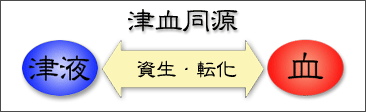津液 ( しんえき / jīnyè / Body Fluids )
1.定義
正常な水分の総称。津と液を含む。
1.1.定義の解説
津液は気や血と同様に人体を構成し、生命を維持するために必要な基本的な物質である。津液のあらわす内容は非常に広範であり、臓腑中の精や、血脈中の血を除く、身体の正常な液体物質が「津液」に属す。
津液は水穀の精微から化生する物質のひとつである。その輸布と排泄は、脾の運化作用・肺の宣散作用による通暢水道・腎の気化作用などが主として行う。これらの臓腑の働きが正常で協調していれば、津液は正常な水分として人体を構成し、生命活動の維持を担う。また、津液は性質と分布部位により、津と液に分けられる。
[文献記載] 他文献の津液に関する定義など。
1.2.津と液
1) 津 ( しん / jīn / Jin )
[定義] 津液のうち、質が清稀で流動性が高く、体表・肌肉・孔竅などに分布するもの。
[解説] 津とは津液のうち、清稀で流動性の高い、つまりさらさらとして動きやすい性質を持った部分をいう。津は体表・肌肉・孔竅(目・耳・鼻・口)に分布し、これらを滋潤・滋養するほか、脈中に注ぎ込んで血を潤す働きがある。
[文献記載] 他文献の津に関する定義など。
2) 液 ( えき / yè / Ye )
[定義] 津液のうち、質が粘稠で流動性が低く骨関節・臓腑・脳・髄などに分布するもの。
[解説] 液とは津液のうち、質が粘稠で流動性が低い、つまりねばねばとして動きにくい性質(特定の部位に注ぎ、分散しない)の部分をいう。液は骨関節・臓腑・脳・髄などの組織に注ぎ込み滋養する働きを持つ。
[文献記載] 他文献の液に関する定義など。
津液は、「津」と「液」の総称である。「津」と「液」は非常に似通っているが、性状・分布・機能が異なり、概念上は明確に区別できる1)2)。
ただし、一般的には、「津」と「液」は同種の物質とされる、また互いに補い転化できるため、「津」と「液」はまとめて「津液」と呼ばれ、厳格な区分は行われない3)。
「津」は以下のような特徴を持つ。[詳細]
o 質が清稀(さらさら)で、流動性が高く
o 体表・皮膚・
肌肉や
官竅に散布し
o 汗として流出したり、血脈内に滲入し
o 滋潤作用を持つ
o
津液を清濁で分ければ清であり、陽に属す
「液」は以下のような特徴を持つ。[詳細]
o 質が粘稠で、流動性が低く
o 骨節や臓腑・脳・髓などに灌注し
o
濡養作用を持つ
o
津液を清濁で分ければ濁であり、陰に属す
1) 『霊枢・決気篇』"腠理発泄、汗出??、是謂津。何謂液。岐伯曰、穀入気満、?沢注于骨、骨属屈伸、洩沢補益脳髄、皮膚潤沢、是謂液"(湊理発泄し、汗出づること??たるを、是れ津と謂う。何をか液と謂う。岐伯曰く、穀入りて気満ち、?沢して骨に注ぎ、骨属屈伸し、洩沢して脳髄を補益し、皮膚潤沢するを、是れ液と謂う)
2) 『霊枢・五?津液別篇』"津液各走其道。故三焦出気、以温肌肉、充皮膚、為其津。其流而不行者、為液" (津波も各おの其の道に走る。故に三焦は気を出だして、以て肌肉を温め、皮膚を充たし、其の津と為る其の流"留"まりて行かざる者は、液と為る)
3) 『類経・蔵象類』"津液本為同類、然亦有陰陽之分、蓋津者、液之清者也;液者、津之濁者也。津為汗而走腠理、故為陽;液注骨而補脳髄、故属陰"(津液は本同類で為るが、然し亦陰陽之分が有る。蓋に津者液之清なる者也、液者津之濁れる者也。津は汗に為って而腠理に走る故陽に属し、液は骨に注い而脳髄を補う故陰に属す。)
2.津液の生成、輸布と排泄
津液の代謝は、生成・輸布・排泄の内容を含んでおり、多くの臓腑の生理機能が協調してつくり出される複雑な過程である1)。
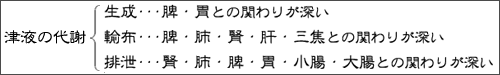
2.1.津液の生成
津液の来源は水穀であり、脾胃の運化やいくつかの臓腑の生理機能により生成される。
以下に津液の生成過程を示す。[詳細]
o 胃は受納と腐熟を主り、水穀から一部の精微を吸収する
o 小腸は清濁の泌別を行い、水穀の精微と水液を大量に吸収し、食物残渣(糟粕)を大腸へ送る
o 大腸は津を主り、伝導の過程で食物残渣(糟粕)中の水液を吸収し、糟粕の糞便への形成を促す
o 胃・小腸・大腸で吸収された水穀の精微と水液は、脾に運ばれ、脾の運化作用により全身に散布される
このように、脾・胃・小腸・大腸など臓腑の生理活動が、津液の生成に関係している。
脾の運化及び胃腸の吸収機能の低下あるいは失調は、津液の生成に影響を与え、津液不足を引き起こす。
2.2.津液の輸布
津液の輸布は、脾・肺・腎・肝と三焦などの臓腑の生理機能の協調より行われる。① 脾 : 脾は津液の輸布に対し、二通りの働きを備える。[詳細]
o 脾は津液を肺に上輸する。(その後、津液は肺の宣発・粛降を通じ全身に散布される)
o 脾は津液を直接全身・臓腑に散布する
脾が運化の働きを失えば、津液の代謝障害が生じ、津液の停滞により痰飲・水腫の形成あるいは脹満痞塞が現れる2)。
また、『内経』には脾の津液の輸布に対する働きとして、「脾気散精」と記載がある。
② 肺 : 肺は宣発・粛降を主り、通調水道を主る。[詳細]
肺は脾が上輸した津液を受け取り、宣発により津液を体表部や身体の上部へ散布し、粛降により津液を身体の下部及び体内の臓腑へ輸布する。同時に臓腑の代謝で生じた濁液を、腎と膀胱へ輸送するこれらの働きから、「肺は水の上源」と呼ばれる。
肺気の宣発と粛降は、津液の輸布の通路を滞りのないよう調節する作用も備えることから「肺主行水」の生理機能を実現している。
肺気の宣発・粛降が失調すれば、津液の輸布の通路はなめらかさを失い津液の運行は障害され、気道で津液が停滞し痰が生じたり、水腫を引き起こす。
③ 腎 : 腎は水臓であり、津液の輸布と代謝に対し主宰的な役割を担っている3)。[詳細]
腎気は津液の輸布・代謝に対し、推動と制御の作用を持つ。腎陽の温煦・蒸騰の性質による発奮作用と、腎陰の涼潤・清熱の性質による制御作用は、以下にあげる臓腑の働きに影響をあたえ、津液の輸布と代謝を主宰する。
o 胃腸の水穀精微の吸収
o 脾気の運化
o 肺気の宣発と粛降
o 肝気の疏泄
o 三焦の決瀆通利
腎気が不足し津液の輸布に対する推動と制御の作用に異常が現れると、正常な津液の輸布に影響をおよぼし、ひどいものでは津液の代謝が停止する。。
また、腎自体も津液の輸布に関与する重要な臓腑のひとつである。臓腑の代謝により生じた濁液は、肺気の粛降作用により腎や膀胱へ輸送され、腎気の蒸化作用を経て、きれいなものは再び吸収され津液の代謝へ戻り、残りの部分は尿液として排泄される。これらの働きは津液の輸布・代謝の維持に対し大変重要な意義を持つ。
④ 肝 : 肝は疏泄を主り、気機をのびやかにする。[詳細]
⑤ 三焦 : 三焦は津液と諸気の通路である。[詳細]
三焦の通利は津液輸布の通路を通暢にし、津液の正常な散布を可能とする。
三焦の失調は、津液の停滞を招き多種の病症を引き起こす。
津液の輸布は主に腎気の蒸化と制御・脾気の運化・肺気の宣降・肝気の疏泄と三焦の通利により行われる。津液の正常な輸布は、多くの臓腑の生理機能の密接な協調により実現する。
2.3.津液の排泄
津液の排泄は、主に尿液と汗液の排出により行われる。このほか、呼気と糞便の排出も津液の排泄の一部を担っている。
津液の排泄は腎・肺・脾などの生理機能との関わりが深く、尿液の排泄は津液の排泄の主な経路であるため、中でも腎の生理作用が重要な意義を持っている。① 腎 : 腎は水臓であり、腎気の蒸化作用は、各臓腑の代謝により生じ、腎や膀胱に下輸された濁液を、清濁の二つに分ける。[詳細]
清らかな部分(清)は再び吸収され全身に散布され、濁った部分(濁)は腎気の蒸化作用により尿液となる。
尿液は膀胱に貯蔵され、一定の尿量に達したとき腎気の推動・発奮作用のもと体外に排出される。貯蔵の過程で尿液が漏れ出さないのは、腎気の固摂作用によるものである。
このように、尿液の排泄も腎気の推動作用と発奮作用に頼っている。
尿液の生成と排泄はいずれも腎気の蒸化作用に頼っており、腎は津液代謝の平衡維持の要である。
腎気の蒸化作用が失調すると、尿少・尿閉・水腫など津液の排泄障害の病変が現れる4)。
② 肺 : 肺気の宣発は津液を体表や皮毛へと輸送する。津液は気の蒸騰作用と発奮作用により汗液を生成し汗孔から体外に排出される。[詳細]
中医学では汗孔を「気門」と呼び、肺気の宣発作用が津液の排泄において重要な働きをしていることを説明している。
このほか、呼気時にもいくらかの水液を排出している。これも津液の排出経路の一つである。
肺気の機能が失調すれば、宣発も失調し汗液の排泄に異常が起こる。
③ 脾・胃・小腸・大腸 : 排便時に、糟粕とともに残余の水分を排泄する。[詳細]
ただし、正常な状況下では糞便中に含まれる水分は大変少ない。
脾胃の運化及び腸道における吸収が失調すれば、水穀中の精微と糟粕は一緒に大腸へ下り糞便は稀薄となる。このとき、水穀の精微が吸収できないだけでなく、胃液・腸液なども流失するため、津液の生成不足・消耗を引き起こし、傷津あるいは脱液の病変を招く。
津液の生成・輸布と排泄の過程は、多くの臓腑が協調し完成する。特に脾・肺・腎の三臓による調節が中心的な役割を果たしている5)。
脾・肺・腎およびその他の関係する臓腑の機能が失調すると、津液の生成・輸布・排泄に影響をおよぼし津液の代謝乱し、津液の生成不足・消耗の過多・排泄の障害・津液の停滞など、多くの病理変化を引き起こす。
1) 『素問・経脈別論篇』"飲入於胃、游溢精気、上輸於脾。脾気散精、上帰於肺。通調水道、下輸膀胱。水精四布、五経並行"(飲 胃に入れば、精気を游溢し、上りて脾に輸る。脾気 精を散じ、上りて肺に帰す。水道を通調し、下りて膀胱に輪る。水精四に布き、五経並び行り)
2) 『素問・至真要大論篇』"諸湿腫満、皆属於脾"(諸もろの湿の腫満するは、皆脾に属す)
3) 『素問・逆調論篇』"腎者、水蔵、主津液"(腎なる者は、水蔵にして、津液を主り)
4) 『素問・水熱穴論篇』"賢者、胃之関也。関門不利。故聚水而従其類也。上下溢於皮膚。故為?腫。"(腎なる者は、胃の関なり。関門 利せず。故に水を聚めて其の類に従うなり。上下して皮膚に溢る。故に?腫たり)
5) 『景岳全書・腫脹』"蓋水為至陰、故其本在腎;水化于気、故其標在肺;水惟畏土、故其制在脾。"(蓋し水は至陰と為す、故に其の本は腎にあり;水気に化し、故に其の標は肺にある;水は惟し土を畏る、故にその制は脾に在る。)
3.津液の機能
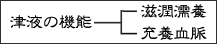
1) 滋潤濡養
津液は液体の物質であり、強い滋潤作用を持つ。また津液は豊富な栄養物質を含み、濡養作用を持つ。
津液の分布と滋潤作用・濡養作用の例を挙げる。[詳細]
o 体表に散布し皮毛や肌肉を滋潤する
o 体内にしみこみ臓腑を濡養する
o 孔窮に輸注して鼻・目・口・耳を滋潤する
o 骨・脊・脳に滲注して骨髓・脊髄・脳髄を充養する
o 関節に流入してを滋潤する
滋潤と濡養の作用は相補相生の関係にある。[詳細]
o 津はその清稀である性質から滋潤作用に優れる
o 液はその粘調である性質から濡養作用に優れる
津液の不足により、皮毛・肌肉・孔竅・関節・臓腑や骨髓・脊髄・脳髄などの組織・器官は滋潤と濡養の作用を失い、臓腑・組織の生理機構は破壊にいたる可能性もある。2) 充養血脈
津液は脈に入り、血の重要な組成成分となる。
『霊枢・邪客篇』では、津液は営気とともに脈中に入り血に化生され、全身を循環し滋潤作用・濡養作用を発揮すると記載がある。[詳細]
津液はまた血の粘度を調節する作用を持つ。
o 血の粘度が増加した時、津液は脈中に入り血を希釈し血量を補充する
o 津液が不足した時、血中の津液が脈外へ出て津液を補充する
この脈中・脈外への津液の出入りは、身体の状態に応じ血の粘度を調節している。これにより正常な血量と血流が保持される。
津液と血はいずれも水穀の精微から化生し、相互に転化・浸透することから、「津血同源」と呼ばれる。
上述1)2)の他、津液の代謝は身体内外の陰陽平衡においても重要な役割を果たしている。[詳細]
例えば、例えば、以下のように体温は恒常的に維持される。
o 暑い気候下、または発熱したとき、津液は汗液と化し体外へ排泄され熱を発散する
o 寒冷な気候下、または体温が下がったとき、津液は腠理を閉じることで外泄されなくなる
。
4.気・血との関係
4.1.気と津液の関係
気と津液の関係は、気と血の関係に類似している。
津液の生成・輸布と排泄は気の昇降出入と気化・温煦・推動及び固摂作用に頼っている。
気の体内での存在は、血だけではなく、津液にも依存している。ゆえに津液も気の担体といえる。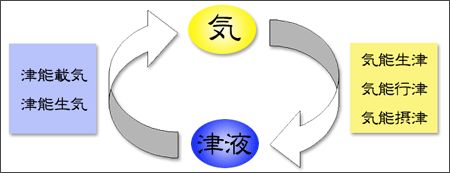
1) 気能生津
気は津液生成の原動力であり、津液の生成は気の推動作用に頼っている。 [詳細]
津液は飲食により摂取した
水穀に由来し、水穀は脾胃の
運化・小腸の分別清濁・大腸の主津など一連の臓腑の生理活動を経て、
精微な液体部分が吸収され、津液に
化生し全身に輸布される。
津液生成の一連の
気化過程では、多くの臓腑の気、特に脾胃の気が極めて重要な働きを果たす。
脾胃など臓腑の気が充実すると、津液を化生する力が増し、津液は充足する。
脾胃など臓腑の気が不足すると、津液を化生する力は弱まり、津液不足を引き起こす。このことから、津液不足の治療時には補気生津の法則を用いることが多い。
2) 気能行津
気は津液の正常な輸布・運行の原動力である。津液の輸布・排泄などの代謝活動から、気の推動作用と昇降出入の運動は切り離せない。 [詳細]
津液は脾胃により
化生され、脾・肺・腎及び
三焦の
気の昇降出入の運動を経て、
推動され全身へ輸布される。その後、代謝過程で生じた廃液と余剰な水分は汗・尿あるいは水蒸気に
転化され体外へ排出される。津液の輸布・転化および排泄の一連の過程は
気化を通じて行われる。
気虚により
推動作用が減弱すると、気化は無力となり、また
気機鬱滞ならば
気化は妨げられる(「気不行水」と呼ばれる)。これらの病態は津液の輸布・排泄障害を引き起こし、
痰・飲・水・湿など病理産物を形成する。
臨床では、痰・飲・水・湿などの病理産物と、それらが引き起こす影響を取り除くため、利水湿・化
痰飲の方法と補気・
行気法を同時に用いることが多い。これは気能行津の理論を応用した具体例である。
3) 気能摂津
気の固摂作用は津液の不要な流出を防いでいる。
また、気は津液排泄に対し節度ある制御をし体内津液量を一定に維持している。 [詳細]
例えば、
衛気は
腠理の
開闔を司り、肌腠を
固摂し、津液を過多に
外泄させない。これは津液に対する
固摂作用の現れである。
気の不足により固摂の力が減弱すれば、多汗・自汗・多尿・遺尿・小便の失禁など多くの病理現象が出現する。臨床では、補気法を用い津液の過多の外泄を抑える方法を用いることが多い。
4) 津能載気
津液は気運行の担体の一つである。[詳細]
血脈中以外での
気の運行は
津液に頼っている。気は津液がなければ、漂い離散し帰るところがない。津液中には気が含まれるため、津液の消耗は同時に気の損傷を招く。
例えば暑熱病証では、津液の消耗だけではなく、汗とともに気も
外泄するので、少気懶言・倦怠感・無力感など
気虚の症状が現れる。大汗・
大吐・
大瀉など津液の大量の消耗時には、気も津液にしたがい大量に
外脱する。このような病態を「気随津脱」と呼ぶ。出汗・嘔吐・下痢などは津液の消耗と同時に、気も損傷する
1)
。そのため、臨床で汗法・吐法と下法を使用する際には注意が必要で、病が治ればすぐに服用を止め、過多の使用により変証を招かないようにする。
津液は気の担体であるため、気は津液に頼り運行する。
津液の輸布・代謝が正常であれば、
気機も伸びやかである。このような関係を「津行則気行(津行けば則ち気行く)」と呼ぶ。逆に、津液の輸布・運行が障害を受けると、気機の
鬱滞・
不暢を引き起こすことが多い。このような病態を「津停則気滞(津停まれば則ち気滞る)」と呼ぶ。「津停則気滞」と前述の「2) 気能行津」で述べた「気不行水」の病理変化は互いに因果関係にある。両者は影響しあい、悪循環を形成し、病情も悪化することが多い。そのため、臨床では治療効果を高めるために、利水薬と行気薬を同時に使用することが多い。
5) 津能生気
水穀から化生される津液は、脾の昇清を通じ肺に上輸され、さらに肺の宣降・通調水道により腎と膀胱に下輸する。津液はこれらの輸布の過程において、各臓腑の陽気が持つ蒸騰・温化の作用により気化される。 [詳細]
臓腑・組織・
形体・
官竅に散布し、生理活動を促進している。そのため、津液不足により気の減少を引き起こすことがある。
4.2.津液と血の関係
1) 津血同源
血と津液はいずれも水穀の精微より化生し、ともに滋養と濡養の作用を備えている。両者は互いに転化し補うことができる。このような関係を「津血同源」と呼ぶ。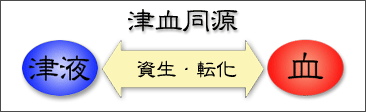
津液は以下の方法で常に血の生成(化血)を行っている。[詳細]
o 津液は心肺の作用の下、脈中に滲入し
営気と結合し
血を生成(化血)する
2)
o
肌肉・
腠理などに散布された
津液は
孫絡に滲入し、血を生成(化血)する
3)
これに対し血は臓腑・組織や官竅を濡潤するだけではなく、時に脈外に滲出し津液と化すことで脈外の津液の不足を補う。[詳細]
また、
津液は汗と化し体外に排泄されるため「血汗同源」と呼ばれる。
以下に示すような原因により、脈外の津液が不足する。
o
水穀の摂取不足
o 脾胃の機能の減弱
o 大汗・
大吐・
大瀉
o 深刻な熱傷
脈外の津液が不足すると、脈中の
血を補充できなくなる。同時に、脈中の津液成分が脈外に滲出し津液の消耗を補充する。
このような場合、以下の病変が発生することがある。
o 血が不足し、濃稠(濃くてドロドロした状態)になる
o 血行の
不暢
この時、放血あるいは破血の療法を行うと、血だけでなく津液も消耗する
4)。
また、血が消耗し津液を補うことができなくなると、脈外の津液が脈中に入り血を補う。このような場合、津液不足に陥ることがある。
このように、血虚の患者に対し発汗法を用いると、津液と血をさらに消耗するおそれがある
4)5)。
津液と血の相互の転化は、次のように総括できる。
o 津液は脈中に滲入し、営気と結合し血と化す
o 血中の津液は営気と分離して脈外に滲出し、津液と化す
1) 『金匱要略心展・痰飲』"吐下之余、定無完気"(吐下の余、宗気無しと定む。)
2) 『霊枢・決気篇』"中焦受気取汁、変化而赤、是謂血"(中焦気を受け汁を取り、変化して赤きを、是れ血と謂う)
3) 『霊枢・癰疽篇』"中焦出気如露、上注谿谷、而孫脈、津液和調、変化而赤為血"(中焦の気を出だすや霧の如く、上より谿谷に注ぎ、而して孫脈に滲み、津液和調すれば、変化して赤く血と為る)
4) 『霊枢・営衛生会篇』"奪汗者無血"(汗を奪う者は血なし)
5) 『傷寒論』"衄家不可発汗"(衄家は発汗すべからず)"亡血家不可発汗"(亡血家は発汗すべからず)
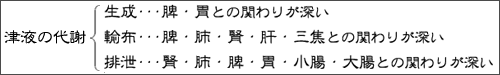
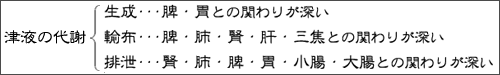
![]()