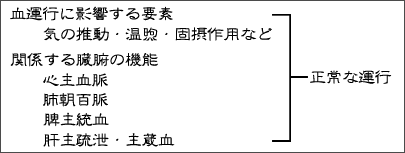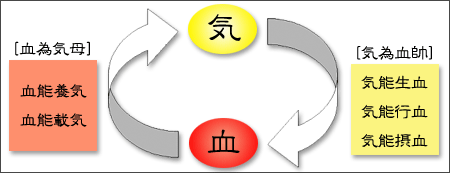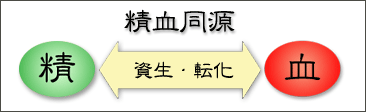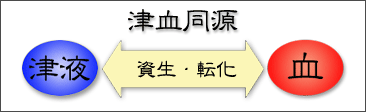血 ( けつ / xiě / Blood )
1. 定義
人体の構成や生命活動を維持し脈中を流れ豊富な栄養を持つ赤色の液体。血液のこと。
1.1. 定義の解説
血は気や津液と同様、人体を構成し生命を維持するために必要な基本物質である。血は水穀の精微より化生した営気・津液を物質的基礎とし、これに心肺の気の働きが加わることで、脈中に注ぎ赤色の液体「血」へと転化する。血は物質的基礎として営気を含むため栄養物質に富んでおり、脈中を巡ることで全身を栄養している。また、血の物質的基礎には営気・津液の他に腎精が存在するが、腎精が血へと化生する過程は営気・津液のそれとは異なる。腎精は腎陽の温煦のもとに脈中に注ぎ血へと転化する。これを「腎精化血」と称する。また腎精と血は必要に応じ直接転化し合う関係(「精血同源」)にある。
[文献記載] 他文献の血に関する定義など。
2. 血の生成
血の材料である水穀精微と腎精は、脾胃・心・肺・腎など臓腑の共同作用による一連の気化過程を経て血へと化生される。 [詳細]
血生成の材料となる基本物質は
水穀の
精である。
『霊枢・決気篇』では、脾胃の
受納・
運化により、水穀から吸収された精微な物質を「汁」と呼んでいる。この「汁」には
営気の素となる
精転物質と
津液が含まれており、この二者が脈中に進入すると赤色の
血に変化すると説明されている
1)。したがって、水穀の精より化生された営気・津液は血化生のための主たる物質基礎であり、血の主な構成成分である。
腎精も血生成の素となる基本物質である
2)。精と血は相互に補い・
転化する関係にある(
精血同源)。そのため、腎精が充実していれば
肝血を
化生し血を充足することができる
3)。
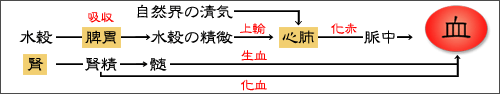
2.1.臓腑との関係
血は各臓腑作用の協調により化生される。血の生成には脾胃・心肺・腎など臓腑の作用が関わっており、このうち脾胃との関係が最も深い。これらの臓腑の作用が正常で協調していれば血は十分に生成され不足することはない。
1) 脾胃
血生成の主な物質基礎である営気と津液は、脾胃の運化・転輸により生産された水穀の精微から作られる。そのため脾胃は「血生化の源」と呼ばれる。 [詳細]
以下二点の状態は、
血化生に直接影響を及ぼす要素である。
o 脾胃の
運化機能
o
水穀摂取による栄養の充足度
脾胃機能の低下・失調あるいは長期に渡る栄養摂取の不良は、どちらも血の生成材料の不足を招き、
血虚の病理変化を引き起こす。
そのため、臨床では血虚を治療する際に、まず根本からのアプローチとして脾胃を調え運化を助けることが大変重視されている。
2) 心肺
心肺は血生成の過程において大変重要な働きを担っている。 [詳細]
血生成の過程を簡単にまとめると次のようになる。
① 脾胃の
運化により得られた
水穀の
精微より
営気・
津液が
化生され
② (営気・津液は)脾により心肺へ
上輸される
③ (営気・津液は)肺により吸入された
清気と結合し
④ 心脈に注ぎ込み、心気の作用により赤色の
血に変化する
清の張志聡は『侶山堂類辨・辨血』の中で心の働きが血の生成に関与していると述べており
4)、『素問・陰陽応象大論篇』においても「心生血(心が血を生む)」と明確な記載があす
。
このほかに、『霊枢・営衛生会篇』では肺の働きが血生成の過程において重要であると指摘している
5)。
寸口脈診は肺脈が血を化生し全身に流しているという認識と、手の太陰肺経が
中焦より起こることが原理の基礎となっている。
臨床では
血虚病証を治療する際に心肺を補い機能を調えることがある。これは上述の理論に基づいている。
3) 腎
腎は精を蔵し、精は髓を生じる。 精髄も血化生の基本物質の一つである。[詳細]
腎精・
腎気が充実すれば、血の生成材料は充足する。また、腎精・腎気の充実は脾胃の
運化を促進させるため、血の化生を助けることにもなる。
腎精不足や腎不蔵精は往々にして血生成の欠乏を引き起こす。そのため、臨床では
血虚病証の治療時に、腎精を補う(補腎益精)方法により、腎精や腎気の作用を増強し、脾胃機能・精血相互の化生(
精血同源)の促進をはかることがある。
1) 『霊枢・決気篇』"中焦受気取汁、変化而赤、是謂血"(中焦気を受け汁を取り、変化して赤きを、是れ血と謂う)
2) 『諸病源候論・虚労精血出侯』"腎蔵精、精者、血之所成也。"(腎は精を蔵し、精なる者は、血の所成なり。)
3) 『張氏医通・諸血門』"精不泄、帰精于肝而化清血。"(精不泄なれば、精は肝へ帰りて清血と化す。)
4) 『侶山堂類辨・辨血』"血乃中焦之汁・・・・・・奉心化赤而為血。"(血は乃ち中焦の汁、・・・・・・心を奉じて赤と化し血と為る。)
5) 『霊枢・営衛生会篇』"此所受気者、泌糟粕、蒸津液、化其精微、上注于肺脈、乃化而為血"(此の受くる所の気は、糟粕を泌し、津液を蒸し、其の精微を化し、上りて肺脈に注ぎ、乃ち化して血と為し)
3.血の機能
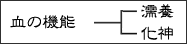
1) 濡養
血は人体が必要とする栄養物質を豊富に含んでいる。各臓腑・経絡など組織・器官は血により濡養・滋潤され正常に働くことができる1)2)。[詳細]
血の濡養作用は特に顔色・肌肉・皮膚・毛髪・感覚・運動などに反映される。
血量が十分で、濡養作用が正常ならば、以下のような反応が現れる。
o 顔色は紅潤
o 肌肉は壮実
o 皮膚は潤沢
o 毛髪は潤沢
o 感覚は鋭敏
o 運動は自在
逆に血量が不十分で、濡養作用が低下すると、以下のような反応が現れる。
o 顔色はくすんだ黄色
o 肌肉はやせ衰える
o 皮膚は乾燥
o 毛髪はつやがない
o 感覚は鈍い
o 運動は無力
※ 濡養と滋潤は対で用いられる。この「濡養」という言葉は近年になって付け加えられたものである。
濡養 … 液体によって栄養する
滋潤 … 液体によって潤す
2) 化神
血は神の基本物質である。神には精神・神志・感覚・思惟などの表現があるが、これら神の活動の発現には血の濡養が必要である3)4)。[詳細]
血と気が充足し血脈と調和すれば血は神を化生することができる。
化神が十分で、神の状態が良好であれば、以下のような反応が現れる。
o 精神は充実
o 神志は明晰
o 感覚は鋭敏
o 思惟は敏捷
一方、なんらかの原因により血量が不足したり、血行に異常があると、精神疲労・健忘・多夢・煩燥・驚悸・神志恍惚・譫妄・昏迷などの症状が現れる。
1) 『難経・二十二難』"血主濡之" (血は、これを濡すを主どる)
2) 『素問・五臓生成篇』(肝は血を受けて能く視、足は血を受けて能く歩む。掌は血を受けて能く握り、指は血を受けて能く摂る)"肝受血而能視、足受血而能歩。掌受血而能握、指受血而能摂"
3) 『素問・八正神明論篇』"血気者、人之神、不可不謹養"(血気なる者は、人の神、謹みて養わざるべからず)
4) 『霊枢・平人絶穀篇』"血脈和利、精神乃居"(血脈和利し、精神乃ち居る)
4. 血の運行
血は脈中を運行し全身を流れることで、その生理機能を発揮する。
血の運行には多くの要素が影響を及ぼしており、多くの臓腑の働きに支えられ正常な運行が保たれている。
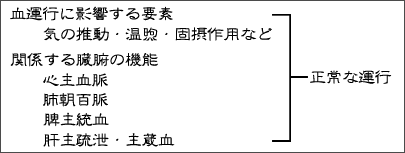
4.1.血運行の影響素因
血は陰に属し静を主る。このため、血の運行には推し動かす動力が必要となる。この動力は主に気の推動作用と温煦作用によるものである。明の虞摶も『医学正伝・気血』の中で"血非気不運(血、気あらざれば運ばず)"と述べている。[詳細]
気の
推動・
温煦作用が減弱すると、血行遅緩・四肢の冷えなどの症状が見られるようになる。
ただし、推動や温煦など陽気の働きだけでなく、陰陽二気の協調があってはじめて
血は常に流動し、一定の速度を保つことができる。
陽気の
推動・温煦の働きだけが強まり、陰気の
寧静・
涼潤の働きによる抑制がなくなると、血の流動は加速し出血を引き起こす。
血が脈中を運行するためには、血が脈外に漏れ出ないようにする働きが必要である。この働きは気の
固摂作用によるものである。
気の推動作用と固摂作用・温煦作用と涼潤作用それぞれの間に協調と平衡が保たれていることが、正常な血運行のための基本的な条件である。
血脈中を血が流れるため、血脈は「血府」と呼ばれる。
血脈に損傷がなく完全で、妨げがなく流れがスムーズであることも、正常な血の運行に重要な要素である
1)。
血の質と量(清濁および粘調の状態を含む)も、正常な運行に影響を及ぼす要素である。
血中に
痰濁が多い場合や血が粘稠であると、血行は
不暢となり鬱滞を引き起こしやすくなる。
その他、
病邪による影響も考慮しなくてはならない。
陽邪の侵入・
火熱の内生などは
陽熱亢盛の病理変化を発生させる。
陽盛により血行を
推動する力が強くなりすぎ
血は
妄行し、血脈を傷つけ脈外への出血を引き起こす。
陰邪の侵襲・陰寒の
内生などは陰寒偏盛の病理変化を発生させる。
陰盛により血脈は渋滞し流れにくくなり、血行は遅緩し、ひどいものでは
瘀血が出現する。
4.2.臓腑との関係
正常な血の運行には、心・肺・肝・脾など臓腑の機能が密接に関わっている。
1) 心
心は血脈を主る。
心気は血を推動し脈中を運行させ全身に巡らせる。心気の充実と推動の作用が正常であるか否かが血の運行において最も重要な意味を持っている。
2) 肺
肺は百脈を朝し治節を主り、心の血脈を主る働きを補助している。[詳細]
気機は肺気の
宣発と
粛降により調節されている。
気の昇降により
血の運行は
推動され全身を巡る。
特に宗気と肺気の働きは重要である。
o
宗気:心脈を貫き血気を巡らせる(行血気)働きを持つ
o 肺気:血の運行における推動と促進の作用を持つ
3) 肝
肝は疏泄を主り、気機を調暢する。これは血の運行がスムーズであるための重要なポイントの一つである。
肝は血の貯蔵と血量を調節する機能(蔵血)を持つ。肝の蔵血作用は疏泄作用と協調し、身体各部位の需要に応じ脈中を循環する血量を調節している。同時に蔵血作用は脈外への血の逸出を防止し、出血の発生を防いでいる。
4) 脾(脾統血)
脾は統血を主る。
脾は血の脈中における運行を固摂し、脈外への出血を防ぐ。
以上のことから、血運行の推動と促進に重要な要素は次のようにまとめられる。[詳細]
血運行の固摂と制御に重要な要素は次のようにまとめられる。[詳細]
また、心・肝・肺・脾など臓腑の機能はそれぞれが単独で働いているわけではなく、相互の協調により、共同で正常な血の運行を保っている。したがって、いずれか一臓腑の働きが失調しても血運行の異常を引き起こすこととなる。[詳細]
臨床では血運行の異常を治療する場合、直接血に対してではなく気を通じてアプローチすることがある。これは以上の理論に基づいている2)。
1) 『霊枢・決気篇』"壅遏営気、令無所避"(営気を壅遏(ようあつ)壅遏して、避くる所なからしむるを)
2) 『温病条辨・治血論』"故善治血者、不求之有形之血、而求之無形之気。"(故に善く血を治す者は、有形の血に之を求めず、無形の気を求める。)
5. 気・津液との関係
5.1.気と血の関係
気と血の間には"気為血帥(気は血の帥)"及び "血為気母(血は気の母)"と呼ばれる密切な関係が存在する。
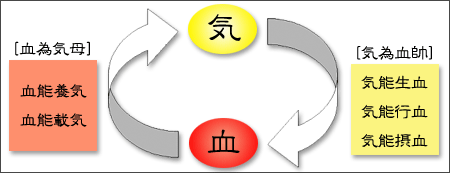
1) 気為血帥(気は血の帥)
「気為血帥」には「気能生血」「気能行血」「気能摂血」の三つの意義が含まれる。
(1) 気能生血
「気能生血」とは気が血の化生(化血)を行う動力であることを指している。ここでいう気とは血の化生に関係する臓腑の気の推動作用や発奮作用を指す。 [詳細]
気が血を化生する過程は以下の二段階からなる。
o 物質基礎である営気・津液・腎精の生成
o 物質基礎から血への転化
気が充実していれば血の化生(化血)はスムーズに行われ、血は十分に生成され、その機能は充実する。一方、気が不足すれば化血の機能は減退し、血虚を引き起こしやすくなる。
臨床上、血虚を治療する際、気能生血の理論に基づき、しばしば補血剤に補気薬を配合し優れた効果を獲得している。
(2) 気能行血
「気能行血」とは血の運行に気の推動作用が不可欠であることを指している。[詳細]
気の推動作用には主に
o 肺の宣発・粛降作用
o 心の主血脈
o 肝の疏泄
などの働きが大きく関わっている1)。そのため、これら臓腑の気の状態が血の運行を左右する。
例えば、以下に示すように、気の推動作用が失調すると瘀血が生じることがある。
o 「気虚」により血の推動が無力となった場合
o 「気機鬱滞」により血に対する推動が滞った場合
また、気機(昇降出入)の失調は血の運行にも影響する。
o 「気逆」により血は気につられ上昇する
o 「気陥」により血は気に従い下降する
したがって、臨床で血行の失調を治療する際、補気・行気・降気・昇提の薬物を配合することが多い。これは気能行血の理論を応用した実践例である。
(3) 気能摂血
「気能摂血」とは血が脈中を循環するために気の固摂作用が必要であることを指す。[詳細]
血に対する気の固摂作用のなかで、脾の統血作用はとりわけ重要な意義を持つ。脾気の状態がこの統血作用を大きく左右する。
脾気が充実していれば統血作用は十分に働き、血は脈外に漏れることなく循行する
脾気虚弱により統血作用が低下すると、血は脈中に留まることができず各種の出血を生じる。(「気不摂血」「脾不統血」と呼ばれる)
したがって、「気不摂血」「脾不統血」などの出血病変を治療する際には、必ず「健脾補気」の方法を用い、益気により統血(摂血)させなければならない。また、臨床では大出血によるショックが発生した場合、この理論に基づき大量の輸血と同時に補気薬を用いる。
2) 血為気之母 (血は気の母)
「血為気之母」には、「血能養気」と「血能載気」の二つが含まれる。
(1) 血能養気
「血能養気」とは、気が充実しその機能を発揮するためには血の絶え間ない栄養提供が必要であることを指す。[詳細]
血の栄養提供は、以下二点のために行われる。
o 気の生成
o 気の機能活動の発揮
これが血の濡養作用の目的であり、血が充実することで気の活動は盛んになる。
臓腑・四肢関節・官竅などの部位が血からの栄養提供を失えば、次のような病変が生じる。
o 気の不足
o 気の機能の喪失による病変
血虚の患者がしばしば気虚の病証を合わせ持つのは、この「血能養気」の法則に準じている。
(2) 血能載気
「血能載気」とは気が血中に存在することで体外に散出せず、全身を運行できることを指す2)3)。[詳細]
大出血を起こした病人は血と同時に気も大量に喪失し「渙散不収」(血が不足し気が散逸し収まらない状態)から、さらに「気髄血脱」(気が浮いて漂うような気脱病変)を引き起こすことがある。
「血為気之母」とは血の気に対する基礎的な作用である「血能養気」と「血能載気」を総括した表現である。
血は陰に属し、気は陽に属す。生命活動はこの陰陽間の平衡と協調により正常に行われる。したがって気と血を調え陰陽の平衡を調えることは疾病の治療によく用いられる常用の治療法則である4)。
5.2. 精と血の関係
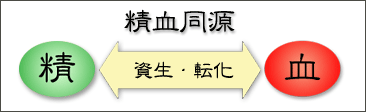
1) 精血同源
精と血はいずれも水穀の精微より化生し充養される物質であり、来源は共通である。両者は相互に補い・転化する関係にあり、どちらも濡養と化神などの作用を備えている。精と血のこの種の関係(来源が同じで、相互に補い転化する関係)を「精血同源」と呼ぶ。[詳細]
精は血化生の基本物質のひとつである。
先・後天の精は臓腑中に分蔵され、臓腑の精となる。臓腑の精は血に流入し血となる。
例えば、
o肝精・心精はそれぞれ肝血・心血に流入し、肝血・心血となる
o脾精は脾が運化・吸収した水穀の精である。その中の精専部分が営気と化し、清稀部分が津液と化し、営気と津液は脈に入り血と化す
o腎精は肝腎の気の推動作用のもと、肝に入り血と化す
このように、先天の精・後天の精が充足していれば、臓腑の精は盛んであり、全身の血も充実する。
腎は蔵精の臓であるため、腎精化血の意義はとりわけ重要である。腎精は血と化し、頭髪を栄養するので「髪は腎の外華」または「髪は血余」と称される。したがって、腎精の虧耗は血虚病証を引き起こし、同時に頭髪がやせつやが無くなり抜け落ちるなどの症状が出現する。
血は後天・水穀の精を主な来源とし、腎精は後天・水穀の精に頼り絶え間なく充養されている。血も精へ化すことができるため絶えず腎の蔵する精を補い滋養し腎精を充実させている。ゆえに、血が充実していれば精は充足し、血が不足すれば精も虧虚となる。
腎の蔵精・肝の蔵血・精能生血・血可化精など、この種の精血間の相互に補い・転化する関係を「精血同源」または「肝腎同源」と呼ぶ。
5.3.津液と血の関係
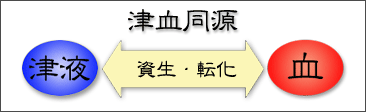
1) 津血同源
血と津液はいずれも水穀の精微より化生し、ともに滋養と濡養の作用を備えている。両者は互いに転化し補うことができる。このような関係を「津血同源」と呼ぶ。
津液は以下の方法で常に血の生成(化血)を行っている。[詳細]
o 津液は心肺の作用の下、脈中に滲入し営気と結合し血を生成(化血)する5)
o 肌肉・腠理などに散布された津液は孫絡に滲入し、血を生成(化血)する6)
これに対し血は臓腑・組織や官竅を濡潤するだけではなく、時に脈外に滲出し津液と化すことで脈外の津液の不足を補う。[詳細]
また、津液は汗と化し体外に排泄されるため「血汗同源」と呼ばれる。
以下に示すような原因により、脈外の津液が不足する。
o 水穀の摂取不足
o 脾胃の機能の減弱
o 大汗・大吐・大瀉
o 深刻な熱傷
脈外の津液が不足すると、脈中の血を補充できなくなる。同時に、脈中の津液成分が脈外に滲出し津液の消耗を補充する。
このような場合、以下の病変が発生することがある。
o 血が不足し、濃稠(濃くてドロドロした状態)になる
o 血行の不暢
この時、放血あるいは破血の療法を行うと、血だけでなく津液も消耗する7)。
また、血が消耗し津液を補うことができなくなると、脈外の津液が脈中に入り血を補う。このような場合、津液不足に陥ることがある。
このように、血虚の患者に対し発汗法を用いると、津液と血をさらに消耗するおそれがある7)8)。
津液と血の相互の転化は、次のように総括できる。
o 津液は脈中に滲入し、営気と結合し血と化す
o 血中の津液は営気と分離して脈外に滲出し、津液と化す
1) 『血証論・陰陽水火気血論』"運血者、即是気。"(血を運ぶ者は、即ちこれ気なり。)
2) 『血証論・吐血』"血為気之守。"(血は気の守を為す。)
3) 『張氏医通・諸血門』"気不得血、則散而無統。"(気は血を得ざれば、則ち散じて統無し。)
4) 『素問・調経論篇』"血気不和、百病乃変化而生"(血気 和せざれば、百病 乃ち変化して生ず)
5) 『霊枢・決気篇』"中焦受気取汁、変化而赤、是謂血"(中焦気を受け汁を取り、変化して赤きを、是れ血と謂う)
6) 『霊枢・癰疽篇』"中焦出気如露、上注谿谷、而孫脈、津液和調、変化而赤為血"(中焦の気を出だすや霧の如く、上より谿谷に注ぎ、而して孫脈に滲み、津液和調すれば、変化して赤く血と為る)
7) 『霊枢・営衛生会篇』"奪汗者無血"(汗を奪う者は血なし)
8) 『傷寒論』"衄家不可発汗"(衄家は発汗すべからず)"亡血家不可発汗"(亡血家は発汗すべからず)
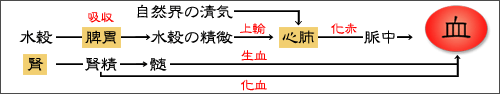
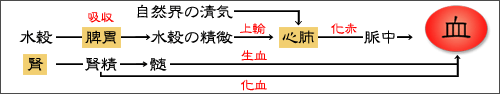
![]()