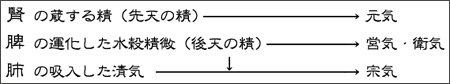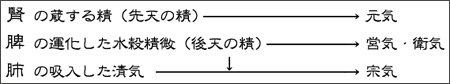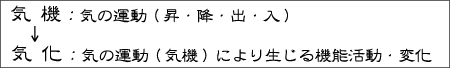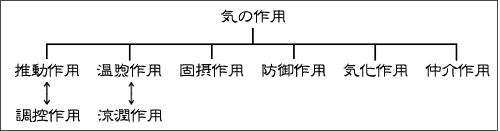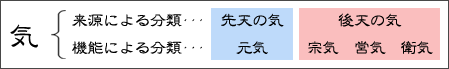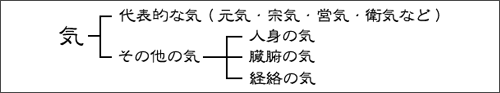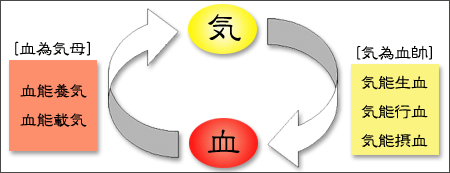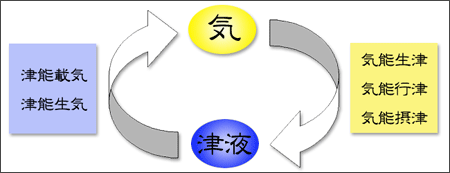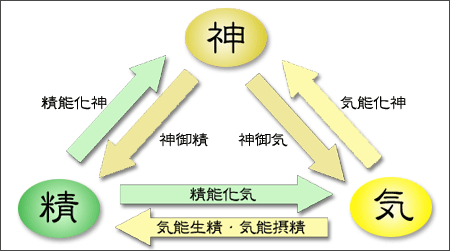気 ( き / qì / Qi )
1. 定義
人体の構成や生命活動を維持し、強い活力を持ち、絶えず運動する精微物質。
1.1.定義の解説
人体の気は肉眼で容易に観察することはできないが血・津液・精と同様、全身の各臓腑経絡などの各組織・器官を流れており、身体中に充ちて人体の構成要素となる他、生理活動の原動力ともなっている。それゆえ気は人体の構成や生命活動を維持し、強い活力(エネルギー)を持ち絶えず運動する精微物質(極めて細かい物質)として位置づけられている。
また、気は以下の基本的な特徴を備える。
o 物質性:気は客観的に存在する物質である
o 運動性:気は絶え間ない運動状態にあり、その運動には規則性がある
o 無形性:気には具体的な形がない物質であり、気体のように拡散している
o 微観性:気は肉眼では観察できない微小物質である
[文献記載] 他文献の気に関する定義など。
[詳細]
気の概念は古人による人体の生命現象の観察を起源としている。例えば「呼吸をするとき気が出入りする」「活動時に汗をかくと熱気が出てくる」「気功鍛錬すると気が流動してくる」など、直視的に捉えた生命現象から推測・抽象化し、「気という、目に見えない
細微な物質が人体を流動している」と考えた。
人体の生命活動において、「気」は絶えず動き新陳代謝に働く。気の運動の停止は、すなわち生命活動の停止を意味する。この現象に深く着目し、その発生・気能・運動法則・形式と、それらが臓腑に及ぼす関係を系統的に捉えたのが、中医学の気理論の成り立ちである。
中医学の気の概念は、当然ながら古代の哲学思想の影響も色濃く受けている。古代の哲学思想における「気」の概念は絶えず動く細微な物質であり、気の昇降・
聚散(集散)・
推動・
調控の特徴が、宇宙万物の発生・発展・変化に及んでいる。これに対し中医学における「気」の概念も同じような特徴を持ってはいるが、あくまで人体に存在する細微な物質であり、身体を構成する基本物質の一つである。このように、中医学の「気」の概念は、古代の哲学思想における宇宙観をも包括した理論とは厳格に区別される。
また「
精」と「気」も人体の基本物質であるが、中医学においては厳格に区別される。「精」とは人体を構成する最も重要な物質であり、人体の生命活動を維持する基本物質である。「気」はこの精から
化生して、生命活動の動力として働く細微な物質である。『黄帝内経』には、いくつもの「精」と「気」の区分と
転化関係の記載がある
1)2)。
ここ十年中国において、「気」の統一概念に関する議論と研究が進められ、「気」は物質としての概念であることが明確化された。また、「気」は精・
血・
津液と異なり肉眼で容易に観察する事はできないが、その運動と変化によって各種の生理現象を引き起こす一種の作用物質であるという点、機能や活動性そのものとは区別される点、などが強調されるようになった。近年「気」の英訳は"Vital Substance(活力的な細微物質)"と表現され、"Energy(エネルギー)"とは異なるものとして説明されている。基礎研究では、近代物理学における量子力学の概念と「気」の概念との相似性、熱力学(エントロピー)理論を用いた「気」の定量化の可能性、生物学的にはATP(アデノシン三燐酸)の生理作用が「気」の作用と類似している点などが指摘されている。
1) 『霊枢・経脈篇』"人始生、先成精" (人始めて生ずるや、先ず精を成し)
2) 『素問・陰陽応象大論篇』"精化爲気" (精は化して気となり)
2. 気の生成
人体の気は各臓腑の作用の協調により生成される。とりわけ腎・脾胃・肺の生理作用との関係が密接である。
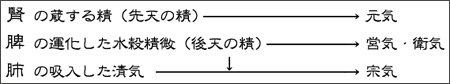
1) 腎(主蔵精気)
腎は精を蔵す(蔵精)。腎に蔵される精(腎精)の主成分は先天の精である。この先天の精は、絶えず後天の精により補われている。 [詳細]
先天の精より
化生する
先天の気は、人体の気の根本である。したがって、腎の蔵精作用と
気の生成とは極めて重要な関係にあるため、腎は「生気の根」と呼ばれる。
腎は
腎精を
封蔵して不要な消耗を防ぎ体内に保存し、気と化すことができる。精が充足すれば気も盛んとなる。
逆に腎の封蔵作用が低下すると、
精ひいては気も不足する。
2) 脾(主運化)
水穀は脾の運化と胃の受納により消化・吸収され水穀の精微となる。水穀の精微は脾の昇清により心肺に輸送され血や津液に化生される。水穀の精微及び血・津液は全て化気することができるため、これらを総称して「水穀の気」と呼ぶ。 [詳細]
水穀の精(微)は
気の材料となり、水穀の気は全身の臓腑・経絡に散布され人体の気の主要な材料となるため、脾胃は「生気の源」と呼ばれる。
脾胃の
受納・
運化などの機能が失調すると、
水穀に対する消化と吸収が低下する。そのため、水穀の精(微)・水穀の気が不足し、全身の気の生成に影響を与える
1)。
3) 肺(主気)
肺は気の生成過程において重要な働きを担っている。 [詳細]
肺は、以下の二つの働きを持つため、「生気の主」と呼ばれる。
o 呼吸の
気を主る:肺は呼吸活動(
清気を吸い
濁気を吐く)を通じ、絶えず自然界の清気を体内に吸入し、同時に濁気を呼出し、体内の気の生成と代謝を請け負っている。
o
宗気の生成を司る:肺は吸入した清気と水穀の気(水穀の精微より
化生し、脾により輸送された)を結合し宗気を生成する。
胸中に集まる宗気には次のような働きがある。
o 呼吸道に上り呼吸を行わせる
o 心脈に注ぎ込み気血を循環させる
o 下って丹田に蓄えられ元気を補う
肺の気を主る(主気)の作用が失調すると、清気の吸入が減少するため、宗気の生成が不足し、全身の気の衰弱を引き起こす。
1)~3) の内容を次のようにまとめることができる。
o 腎の生理機能と、先天の気の生成には密接な関係がある。
o 脾胃・肺の生理機能と、後天の気の生成には密接な関係がある。
o 腎・脾胃・肺などを含む多くの臓腑の機能が密接に協調し、はじめて人体の気は絶え間なく生成される。
腎・脾胃・肺など臓腑の生理機能に異常や協調の失調が生じると、気の生成やその機能に影響を及ぼす。
1) 『霊枢・五味篇』"故殺不入半日、則気衰、一日則気少矣"(故に穀入らざること半日なれば、則ち気衰え、一日なれば則ち気少なし)
3. 気の運動と気化
気は運動する特徴を持ち、休むことなく運行することで新陳代謝を発奮・制御し、生命過程を推動する。気の運動が止まり、新陳代謝における気化の過程が停止することは、生命活動の終了を意味する。
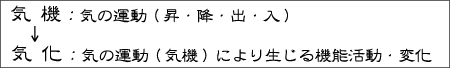
3.1. 気機 ( きき / qìjī / Qi movement )
1) 気機の概念
[定義] 気の運動を指す。すなわち昇・降・出・入のこと。
[解説] 気は人体内を絶えず運動し、各臓腑・経絡など全ての組織・器官に行き渡ることで生命活動を維持している。気機とは人体内を絶えず運動する気の巡りのことをさし、昇降出入は気の運動の方向性を4つの基本的な形式で言い表したものである。
[文献記載] その他文献の気機に関する定義など。
2) 気の運動の基本形式
気の運行形式は、気の種類や機能の違いにより異なる。 [詳細]
ただし、総じて言えば昇・降・出・入という四種の基本形式に
帰納できる。
o 昇:上へ向かう
気の運行を指す
o 降:下へ向かう気の運行を指す
o 出:外へ向かう気の運行を指す
o 入:内へ向かう気の運行を指す
呼吸を例に挙げれば次のように考えられる。
o
清気の吸入は内へ向かう運動なので「入」
o
濁気の呼出は外へ向かう運動なので「出」
o 吸気は気流が下へ向かい鼻・喉を経て肺に入るので「降」であり「入」
o 呼気は肺から上へ向かい喉・鼻を経て体外に排出されるので「昇」であり「出」
気の運行における昇と降・出と入など、正反対でありながらも統一的な矛盾した運動は、体内に広く存在する。
肝・脾は昇を主り、肺・胃は降を主るなどのように、ある臓腑の一部の生理特徴に焦点を当てるとある程度の偏りはあるが、体全体の生理活動から見れば、昇と降・出と入の間には必ず協調と平衡が保たれている。
このような平衡が保たれ、正常な気の運動が存在し、臓腑はそれぞれの生理機能を発揮する。
気機の昇降出入の協調と平衡は正常な生命活動を保つための重要な要素である。
以下の二点は正常な気の運動に必要な条件である。
o 気の運動がのびやかで滞りがないこと
o 昇降出入の運動の間に協調と平衡が保たれていること
この二点を備えた気の運動状態を「気機調暢」と呼ぶ。
3) 気の運動の意義
人体の生理活動は気機(昇降出入)に頼っているため、気機には非常に重要な意義がある。 [詳細]
以下にその例を挙げる。
o
先天の気・水穀の気・吸入した
清気などは、全て昇降出入の運動を経て全身に散布され、生理機能を発揮する
o
精・
血・
津液など液状の物質も
気の運動により体内を運行・流動し、全身を
濡養する
o 臓腑・経絡・
形体・
官竅の生理機能は気の運動に頼り完全となる
o 臓腑・経絡・形体・官竅の相互間の連携や協調は、気の運動により実現する
また、人の清気の吸入と濁気の呼出や食物や水分の摂取と糞便・尿・汗の排出などのような、人と自然界の間の連携や適応も、昇降出入の運動がなければ成り立たない。
気機(昇降出入)は、生命活動の根本であり、気機が止まれば、生命活動は停止する1)。
4) 臓腑の気の運動法則
臓腑・経絡・形体・官竅は全て気の昇降出入が行われる場所である。また気機(昇降出入)は臓腑・経絡・形体・官竅における生理活動の中でのみ観察できる。
臓腑の気の運動法則は独特であり、臓腑の生理活動の持つ特徴や、臓腑の気の運動の趨勢を現す。
臓腑の気機(昇降出入)は、「昇はやがて降となる・降はやがて昇となる・昇中に降有り・降中に昇有り(昇已而降・降已而昇・昇中有降・降中有昇)」の特徴を持ち、対立と統一・協調と平衡の法則を体現している。
[詳細]
以下にその具体例を挙げる。
① 五臓の
気の運動
趨勢には次のような特徴が見られる。
o 心肺は上に位置するので、降の特徴を持つ
o 肝腎は下に位置するので、昇の特徴を持つ
o 脾胃は中に位置するため、上下に通じ昇降
転輸の要となる
② 六腑全体としては降の特徴を持つ。加えて、わずかであるが昇の特徴を備えている。
o六腑は水穀の伝化を行っており、六腑の中に水穀を留めないため、「通をもって用となし、降をもって順となす(以通為用、以降為順)」と言われる(降の特徴)
o水穀の消化と吸収の過程において、水穀の精微・津液などの抽出を行う(昇の特徴)
③ 臓腑間の関係をみると、それぞれが昇降出入の平衡を保っていることがうかがえる。
o 肺の出気(出)と腎の納気(降)
o 肝の昇発(出)と肺の粛降(降)
o 脾の昇清(昇)と胃の降濁(降)
o 心腎相交(心火の昇と腎陰の降) など
④ 一つの臓腑中でも、それぞれが昇と降の働きを持ち、平衡を保っている。
o 肺の宣発(昇)と粛降(降)
o 小腸の分清別濁(昇と降) など
各臓腑の気機が調暢であれば、臓腑間の昇降出入の運動は、協調のとれた統一体の中にあるといえる。
また、臓腑の気機が調暢であれば、人体が絶えず自然界から生命活動に必要な物質を摂取できる。物質代謝とエネルギー転換の平衡は、気化作用・昇清降濁・精微の摂取・廃棄物の排泄などを通じて維持され、生命活動を促進している。
5) 気の運動失調の表現形式
気機の異常により、昇降出入の協調と平衡が失われた状態を「気機失調」と呼ぶ。
気の運動形式は多種多様であるので、気機失調にも多くの表現がある。 [詳細]
代表的な気機失調を以下に挙げる。
o
気機不暢:
気の運行が阻害され通じにくい状態
o 気滞:気の運行の阻害が甚だしく、局部で滞り通じない状態
o 気逆:気の上昇が強すぎる、或いは下降が弱すぎるため、気が
上逆した状態
o 気陥:気の上昇が弱すぎる、或いは下降が強すぎるため、気が
下陥した状態
o 気脱:気の外出が強すぎるため、内に引き留められず、気が
外脱した状態
o 気閉:気の外出が弱すぎるため、気が内に
鬱結し閉塞した状態
このような「気機失調」の状態と機序を把握すれば、容易にそれらに応じた治療法則を立てることができる。
3.2. 気化 ( きか / qìhuà / Qi transformation )
1) 気化の概念
[定義] 気の運動により生じる機能活動・変化を指す。
[解説] 気化とは気の運動(気機)により生じる新陳代謝の過程であり、物質の転化とエネルギー転化の過程でもある。また、気は身体中に充ちて生理活動の原動力となるだけではなく、推動作用や温煦作用などいくつかの作用を有しており、その一つに気化作用がある。例えば水穀から生理活動の原動力となる気の生成、気から血・津液・精・神などへの転化、汗や尿など排泄物の生成などの各種変化はすべて気化によるものである。
[文献記載] 他文献の気化に関する定義など。
[詳細]
以下に挙げる事柄はすべて「気化」に属す。
o
精微物質の
化生と輸布
o 精微物質間・精微物質とエネルギーの間の相互変化
o 老廃物の排泄 など
中医学の「気化」は、人体の
気の運動により引き起こされた
精気血津液などの物質とエネルギーの新陳代謝を指す。「気化」は生命の最も基本となる特徴の一つであり、古代哲学における宇宙万物の発生・発展・変化という概念とは区別される。
2) 気化の形式
気化とは以下三点の過程であると言える。
o 体内物質の新陳代謝の過程
o 物質転化の過程
oエネルギー転化の過程
したがって、精気血津液それぞれの代謝及び相互転化は、代表的な気化であると言える2)。
[詳細]
以下にその具体的な例を挙げる。
o
精の生成には
先天の精の充実と
後天の精(水穀の精)の
化生の二つが含まれる
o
精の
気への化生(
化気)には、先天の精から
元気への、
後天の精から穀気への化生が含まれる。また、穀気は更に
営気・
衛気へ分化する
o 精は
髄を化生し、髄は骨を満たし消耗する、あるいは脳に集まり
化神する
o 精と
血は相互に化生・
転化することができ「精血同源」と呼ばれる
o
津液と血は相互に化生・転化することができ「津血同源」と呼ばれる
o
血の生成やその化気・
生神
o 津液の生成とその
化汗・
化尿
o
気の生成と代謝(エネルギー・熱量への転化及び生血・
化精・化神、臓腑の気や経気への分化などを含む)
これら気化の過程の
発奮や連携は、各臓腑の機能により維持されている。つまり、臓腑の活動が協調していれば、気化の過程は正常に行われる。
3.3. 気機と気化の関係
生命活動は気の絶え間ない運動により営まれる。気化も生命活動の一部であることから、気機は気化の原動力であると言える。 [詳細]
気化過程の発生・進行には、
気の昇降出入、および気の陰陽双方の相互作用が必要である。気は絶えず運動しているので、気化過程も絶えず行われる。
別の角度から見れば、気の昇降出入運動は気化の過程に含まれている。
3)。
気機及びそれが維持する気化過程は生命過程において、途切れることなく恒久的に存在する。気機は新陳代謝の協調と安定、秩序ある生命過程を維持している。気の運動や気化過程の停止は生命活動の終結を意味する。
1) 『素問・六微旨大論篇』"出入廃、則神機化滅、升降息、則気立孤危。故非出入、則無以生長壮老已。非升降、則無以生長化収蔵。是以升降出入、無器不有"(出入廃さるれば、すなわち神機は化して滅し、升降息めば、すなわち気立は孤にして危うし。ゆえに出入するにあらざれば、すなわちもって生・長・壮・老・已するなく、升降するにあらざれば、すなわちもって生・長・化・収・蔵するなし。ここをもって升降・出入は、器としてあらざるなし)
2) 『素問・陰陽応象大論篇』"味帰形、形帰気、気帰精、精帰化。精食気、形食味、化生精、気生形。味傷形、気傷精。精化為気、気傷於味"(味は形に帰し、形は気に帰し、気は精に帰し、精は化に帰す。精は気に食なわれ、形は味に食なわれ、化は精を生じ、気は形を生ず。味は形を傷り、気は精を傷る。精は化して気となり、気は味に傷らる)
3) 『素問・天元紀大論』"物生謂之化、物極謂之変"(物の生ずるこれを化と謂い、物の極まるこれを変と謂い)
4. 気の作用
気の作用は、気の「活力的に絶えず動く」という特徴を大きく反映している。
以下に挙げる諸々の気の作用は、互いに密接に協力し、人体の生理状態を維持している。よって、これらの作用は生命活動の基本的な条件である
。
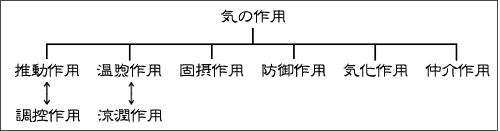
1) 推動作用 ( すいどう / tuīdòng / Driving )
[定義] 気の持つ人体の生長発育および臓腑経絡などの生理活動を促進・発奮する作用。
[解説] 気の作用の一つ。気は強い活力(エネルギー)を有しており、人体内を絶えず休むことなく運動している。気はこの運動の過程で人体に活力を与え生長・発育を促している。また気は臓腑・経絡などの各組織・器官の働きを促進・発奮し、正常な生理機能を発揮させていると言える。その他、気には血・津液・精などの液状物質を押し流す原動力としての働きがある。気のこのような働きを推動作用という。
[文献記載] 他文献の推動に関する定義など。
[詳細]
気の推動作用とは、
気の強い活力により行われる以下の働きを指す。これには直接的な働きと間接的な働きがある。
o
精・
血・
津液などの液状物質の代謝を促進する(直接的)
o 人体の臓腑経絡における正常な生理活動を推し進める(間接的)
したがって、精血津液の生成と運行・輸布、人体の成長と発育、および臓腑経絡の生理活動などは気の
推動作用に依存している。
例えば、元気の持つ推動作用は、人体の生長と発育、生殖機能と各臓腑・組織の働きを促進することができる。もし、元気が不足すれば推動作用が減弱し、人体の生長と発育の遅れ、生殖機能の衰え、あるいは早老をまねく。同時にまた、臓腑・経絡の生理活動の低下を引き起こし、生命活動は減弱し無力となる。このほか、精の生成と施泄、血の生成と運行、津液の生成と輸布・排泄など、多くの生理活動は気の推動作用に頼り正常に行われる。
気の推動作用の減弱は、精の生成不足と施泄の障害、血と津液の生成不足および運行・輸布の遅れなどを引き起こす。
1') 調控(制御)作用
気の調控(制御)作用は、推動と対照的な人体の生長と発育および臓腑経絡などの生理活動を制御・抑制する作用を指す。 [詳細]
人体の機能活動には協調と平衡が必要で、そのためには
推動だけでなく制御する作用も必要である。諸々の
気を陰陽で二分すると、陽に属す気である「
陽気」と、陰に属す気である「
陰気」に分けられる。
o 陽気:発揮・
推動・興奮・
昇発の作用を備える気
o 陰気:安静・抑制・
粛降の作用を備える気
これら「陽気」「陰気」の機能は協調して生命活動を安定させ、過剰な働きを抑制しながらも不足しないよう維持している1)2)。このように、「陽気」「陰気」の機能の協調は、人体の生長と発育および生殖能力の安定、臓腑・経絡の機能の協調、精血津液の生成および運行・輸布を秩序のある安定した状態に保っている。 例えば、陰気の安静・抑制などの作用が減弱すれば、相対的に陽気の推動の作用は亢進し、臓腑の機能は抑制が効かずに亢進する。具体的には精血津液の代謝が亢進し、精血津液の消耗が激しくなり遺精・多汗・出血・煩躁・失眠などの症状が現れる。
2) 温煦作用 ( おんく / wēnxù / Warming )
[定義] 気化によって産生した熱量により人体を温める作用。
[解説] 気の作用の一つ。気には熱を産生する働きがあり、人は気の温煦作用により体温を一定に保ち正常な生理機能を行っている。各臓腑・経絡・血や津液などの全ての組織・器官は、気が産生した熱量により温められ、スムーズに生理機能を発揮している。気のこのような働きを温煦作用という。
[文献記載] 他文献の温煦に関する定義など。
[詳細]
温煦作用の主な役割は以下の通りである。
o 人体の体温を生理的な一定の温度に維持させる
o 臓腑・経絡・
形体・
官竅の生理活動を助ける
o
精血津液の正常な
施泄・循行・輸布を助ける(「暖めれば流れ、冷えれば凝集する」の特性から)
温煦は「陽気」の作用である3)。陽気が不足すれば熱の生産は減少し、虚寒性の病変が現れるため、畏寒、体温の低下、四肢の厥冷、臓腑の生理活動の減弱、精血津液の代謝の減弱、運行の遅れなどの症状が出現する4)。
2') 涼潤作用
気の涼潤作用は、温煦と対照的な人体を冷やす作用を指す。 涼潤は「陰気」の作用である。陰気は寒涼・柔潤・制熱などの特徴を持ち、陽気と協調し、体温を一定に保ち臓腑の機能を安定させ、気血津液の滑らかな運行・輸布と代謝を助けている。 [詳細]
涼潤作用は「
陽気」の持つ
温煦作用と密接な関係があり、気の
推動-
調控作用と同様、陰陽の対立・統一の関係にある。
陰気の涼潤作用が減退すると、微熱・
盗汗・
五心煩熱・脈細数などの五臓機能の興奮による症状と、
精血津液代謝の亢進による「
虚熱」の症状が出現する。
3) 固摂作用 ( こせつ / gùshè / Containing )
[定義] 気による体内の液体物質を統轄し不要な流出を防ぐ作用。
[解説] 気の作用の一つ。体内には血・津液・精などの液体物質が存在する。これらが規則的な分泌と排泄を行うことで生理機能は発揮される。この規則的な分泌と排泄を維持するため、気は血の脈外への漏出、汗や尿などの過多な排泄、精の不要な流失を防ぐように働く。気のこのよう働きを固摂作用という。
[文献記載] 他文献の固摂に関する定義など。
[詳細]
固摂作用は以下の三つの方面に働く。
o
血の統摂:脈中において血を正常に運行させ、その脈外への漏出を防ぐ
o 汗・尿・唾液・胃液・腸液の固摂:これらの分泌と排泄を規則的に制御し、過多な排出や、不要な流出を防止する
o 精液の固摂:精液がみだりに排泄されることを防ぐ
気の固摂作用が減弱すれば、体内の液状物質は失われる。
固摂低下の病証には以下のものがある。
o 「気不摂血」:血に対する固摂作用の低下から、各種の出血を引き起こす。
o 「気不摂津」:津液に対する固摂作用の低下から、自汗、多尿、小便不利、流涎、嘔吐清水、泄瀉滑脱など、津液が流出を引き起こす。
o 「気不摂精」:精に対する固摂作用の低下から、遺精、滑精、早泄など病理的な精液の排泄を引き起こす。
4) 防御作用(防衛) ( ぼうぎょ / fángyù / Defending )
[定義] 気の持つ外邪の侵入を防ぎ抵抗する作用。
[解説] 気の作用の一つ。気は人体の表面、つまり体表(肌膚)をコーティングするように保護し、外邪の侵入を防いでいる。また気は万が一、外邪が人体内に侵入した場合、これに抵抗し駆除するように働く。気のこのような働きを防御作用という。
[文献記載] 他文献の防御に関する定義など。
[詳細]
防御作用とは
肌表を護衛し外邪の侵入を防ぐだけでなく、同時に人体に侵入した
病邪を駆除する作用である
5)。
防御作用が主に
衛気が果たす働きである。防御作用が強ければ邪気は侵入できない
6)。しかし防御作用が低下すると、邪気にあらがう力が足りず、邪気は容易に侵入し発病させる。また、『素問・評熱病論篇』には「邪のあつまる所、其の気必ず虚す」と記載がある
7)。邪気がある部位に侵入した時、正気はその部位に集まり邪気に対する防御と駆除の働きを発揮する。したがって、気の防御作用が正常であれば邪気は簡単に侵入できない。また、邪が侵入しても発病しにくく、治りやすい。このように防御作用は疾病の発生・発展・転帰を左右している。
5) 気化作用 ( きか / qìhuà / Qi transformation )
[定義] 気の運動により生じる各種変化を指す。
[解説] 気化作用とは、気の運動を通じ各種の変化を生み出す働きを指す。具体的に言えば、気・血・津液と精など、それぞれの新陳代謝及び気の作用により発生する相互の転化を指す。
気化とは気の運動(気機)により生じる新陳代謝の過程であり、物質転化とエネルギー転化の過程でもある。また、気は身体中に充ちて生理活動の原動力となるだけではなく、推動作用や温煦作用などいくつかの作用を有しており、その一つに気化作用がある。例えば水穀(飲食物)から生理活動の原動力となる気の生成、気から血・津液・精・神などへの転化、汗や尿など排泄物の生成などの各種変化はすべて気化によるものである。
[文献記載] 他文献の気化に関する定義など。
6) 仲介作用
気の仲介作用とは、気が情報を誘導・伝導し、肉体の整体関係をつなぎ止める働きを指す。 [詳細]
各臓腑・組織・器官はみな体内で相対的に独立し存在しているが、これらの間には充満する
気が存在している。気は人体それぞれの臓腑・組織・器官の間で、相互の関係を仲介する役割を持つ。
気はまた情報を誘導・伝導する手段でもある。体内の各種の生命情報は、気の昇降出入運動を通じて誘導・伝導される。これにより各部位の間に密接な関係を築くことができる。
例えば、臓腑の各種情報は仲介作用によって誘導・伝導され体表に反映される。また、気は臓腑の各種情報を媒介して相互に伝達し、体内の情報伝達の手段を構成する。
以下に例を示す。
o 臓腑の精気の盛衰は、気の負荷と伝導を通じ体表に呼応する
o 臓腑の間の情報伝達は、気を媒介として経絡あるいは
三焦などの通り道を通じ伝達される。これにより臓腑間の関係は強化され協調を維持している
鍼灸・按摩やその他の外治法の刺激や情報も、気の誘導・伝導を通じ臓腑に伝わり、生理活動を調節する目的を果たしている。
すなわち気は生命情報の担体(キャリアー)であり、これは臓腑・
形体・
官竅の間の連絡を仲介する作用を備えている。
1) 『証治准縄・雑病・諸気門』"一気之中而有陰陽、寒熱昇降動静備于其間"(一気の中に陰陽有り、寒熱昇降動静を其の間に備う。)
2) 『医原・陰陽五根論』"陰陽五根、本是一気、特因昇降而為二耳"(陰陽互根、本は是れ一気なる。特に昇降に因りて二を為すのみ。)
3) 『医ヘン(石扁)・气』"陽気者,温暖之気也。"(陽気は温暖の気なり。)
4) 『諸病源候論・冷気候』"夫蔵気虚,則内生寒也" (夫臓の気虚、すなわち寒を内に生ずるなり。)
5) 『素問・刺法論篇・遺篇』"正気存内、邪不可干"(正気内に存し、邪干すべからず)
6) 『医旨緒余宗気営気衛気』"衛気者、為言護衛周身、温分肉、肥腠理、不使外邪侵犯也"(衛気は、周身の護衛を言い。分肉を温め、腠理を肥し、外邪をして侵犯させざるなり。)
7) 『素問・評熱病論篇』"邪之所湊、其気必虚"(邪の湊まる所、其の気必ず虚す)
5. 気の分類
人体の気は、生成の来源と分布部位や機能により分類できる。
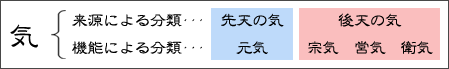
5.1. 来源による分類
1) 先天の気 ( せんてんのき / xiāntiānzhiqì / Congenital Qi )
[定義] 先天の精から化生した気で、人体生命活動の原動力。元気のこと。
[解説] 父母の生殖により先天的に授かり、腎に蔵される先天の精が化生した気。先天の気は、内は臓腑、外は腠理・肌肉・皮膚にいたるまで、全身に分布している。臓腑経絡など各組織・器官は先天の気の作用を受け機能を発揮している。それゆえ先天の気は生命活動の原動力といわれる。
[文献記載] 他文献の先天の気に関する定義など。
2) 後天の気 ( こうてんのき / hòutiānzhiqì / Acquired Qi )
[定義] 後天の精と清気より化生した気で、宗気・営気・衛気を含む。
[解説] 後天の精より化生した気を水穀の精気という。これがさらに化生され営気・衛気となる。また宗気は水穀の精気に自然界から吸入された清気が結合し生成されたものである。
[文献記載] 他文献の後天の気に関する定義など。
5.2. 機能による分類
1) 元気・原気 ( げんき / yuánqì / Promordial Qi )
(1) 元気の概念
[定義] 人体の最も根本・最重要の気であり、生命活動の原動力であり、丹田に蔵される。先天の気・真気のこと。
[解説] 人体の気はその来源や分布部位、機能の違いなどにより、それぞれ異なる名称が付けられている。その中でも元気は来源を先天の精とし、全身に分布し、人の成長や発育を促し、臓腑経絡などの各組織・器官を温めて生理活動を始動させ、生命活動の原動力となる。それゆえ、元気は人体の最も重要な気とされる。また、元気は父母より受け継いだ先天の精が化生した気であることから、先天の気ともいう。『黄帝内経』には「真気」と記載されている。
[文献記載] 他文献の元気に関する定義など。
(2) 生成と分布
元気の生成と分布は以下の通りである。
o 腎において1)先天の精より化生し、水穀の精気により補充され
o 三焦を通じ全身を流れる [詳細]
元気は、腎中に蔵された
先天の精より化生される。
その先天の精は、父母の生殖の
精より
稟受したもので、胚胎期にはすでに存在する。出生後は脾胃の
化生する水穀の精により滋養と補充を受け充実し、十分に元気を化生できる。
したがって、元気が充実で盛んであるか否かには、以下の状態が影響する。
o 先天の精:父母に由来する
o 後天の精:脾胃の運化作用・飲食により取り込む栄養に関係する
先天の精の不足により元気が虚弱であれば、後天の育成・補充により元気を補うことができる2)。
元気は三焦を通じ全身を流れる3)。
元気は腎に起こり、三焦を通路とし、内は五臓六腑、外は肌膚腠理に至るまで全身のあらゆる部位を循行し、それら組織・器官の働きを発揮させる。そのため元気は生命活動において最も根本的で、最も重要な気であると言える。
(3) 生理機能
元気には以下二つの生理機能がある。
① 人体の生長・発育と生殖機能を推動・調節する [詳細]
元気と
腎気の機能はほぼ同じであり、人体の成長・発育と生殖機能を
推動する。
腎精の主な成分は
先天の精であり、腎精が
化生した腎気は主に
先天の気である。したがって、元気と腎気の構成成分はおおよそ同じであり、発揮する機能も類以している。
元気の盛衰は身体の
生・長・壮・老・已の自然法則として現れる。
幼年期から腎精は先天の精を以て基礎とし、
後天の精の補充を受けて徐々に充実し、元気を化生して人体の生長と発育を促進する。
幼年期から青年・壮年期までの時期は、腎精が一定の水準まで充実し、十分な元気が化生され、身体を発育し、肉体を丈夫にして、筋骨を強靱にする。これと同時に生殖能力を備える。
老年に達すると、腎精は生理・病理的に消耗し徐々に衰え、元気の化生もそれにつれ減少する。肉体には老化の現象が現れ、生殖機能も
衰退する。元気が
衰亡にまで至ると、命の終わりを迎える。
したがって、元気不足になると生長・発育が遅れ、生殖機能の低下および早老などの病変が出現しやすくなる。
② 各臓腑・経絡・形体・官竅などの生理活動を推動・制御する [詳細]
元気は
三焦を通じ、全身に散布し、全ての臓腑・経絡・
形体・
官竅の生理活動を全面的に促進・制御している。
また、元気の働きには「陽」「陰」の両面が存在する。
o 「陽」:心
神を興奮させる、
推動・興奮・
化気・
温煦などを発揮させる機能
o 「陰」:心神を寧静させる、
寧静・抑制・成形・
涼潤などを発揮させる機能
このように、元気は
元陰と
元陽に分けることができ、全身の陰陽に影響をおよぼしている。
元気は命門に起こる4)。
命門の水火と元気の陰陽の間に協調と平衡があり、臓腑機能は「陰平陽秘」の健康状態を保つことができる。
まとめて言えば、身体の生命活動は全て元気の推動と制御の下に行われている。
元気は生命活動の原動力であり、元気の不足あるいは元陰・元陽の平衡の失調は、深刻な病変を招く。
2) 宗気 ( そうき / zōngqì / Thoracic Qi )
(1) 宗気の概念
[定義] 後天の気の一つ。水穀の精気と自然界の清気が結合し、胸中に集まった気。心肺の活動を支える働きをもつ。
[解説] 後天の気の一つ。飲食物より得られる水穀の精気と、肺を経て吸収される自然界に存在する清気が結合し、胸中に集められたのが宗気である。宗気には主に心血の運行と肺の呼吸作用を支える役割がある。
[文献記載] 他文献の宗気に関する定義など。
(2) 生成と分布
宗気には二つの来源がある。
o 水穀の気:脾胃が運化した水穀の精より化生したもの
o 清気:肺が自然界から吸入した大気
この両者が結合し宗気となる。 [詳細]
したがって、脾の
運化・
転輸作用と肺の主気・司呼吸作用が正常であるか否かが、宗気の生成・盛衰と直接関係する。
宗気は胸中に聚まり、上って呼吸道に出て、心脈に注ぎ込み、三焦に沿って下行し全身に散布する5)。
[詳細]
宗気は一方で、上って肺に出で、喉や呼吸道を通ることで呼吸を促進させる。
もう一方では、心脈に注ぎ込み、血行を推動する。
また、
三焦は諸
気の運行の通路である。宗気は三焦に沿って下へ向かい
臍下丹田まで運行し、先天の気、つまり元気を助ける。
その他に『霊枢・刺節真邪篇』には、宗気は
気海より下に向かい気街(足の陽明経の鼠径部)に注ぎ込み、さらに下行し足に至ると記載がある。
(3) 生理機能
宗気には以下三つの生理機能がある。
① 行呼吸(呼吸を推動する) [詳細]
宗気は呼吸道に上り、肺の呼吸を促進する。
したがって、呼吸も言語も発声もすべて宗気と関係がある。
宗気が充実していれば呼吸は安定し、言語は明瞭、声は大きくよくとおる。宗気が不足すると、呼吸は浅くて速く微弱になり、言語は不明瞭、声は低く弱くなる。
② 行血気(血運行の推動を促進する) [詳細]
宗気は心脈に注ぎ込み、心が
血運行を
推動する働きを促進する。
したがって、
気・血の運行の基本的な要素である心の鼓動の力とリズムはすべて宗気と関係があると言える。
宗気が充実していれば脈拍はゆったりとし、リズムは一定で力がある。宗気が不足すると脈は慌ただしく、リズムは不規則、あるいは微弱で力がなくなる。
虚里は左乳下に発し、心尖拍動の部位に相当する
6)。この部位の拍動から宗気の状態を推測することができる。宗気が充実してれば、拍動は正常である。逆に拍動がせわしなく、服の上から見えるほど強ければ、宗気が大虚であることを現す。また拍動の消失は、宗気が尽きたことを現す。
しかし、現在の臨床では、虚里よりも
脈象により宗気の盛衰を推測する方法が一般的である。
宗気は心脈の気・血の運行を助けるので、宗気の不足は往々にして血行の
鬱滞を招く。
宗気は呼吸運動・血の循行を促進する働きを備えているため、気血の運行や肢体の温かさと活動・視覚や聴覚などの感覚・発声及び脈拍の強弱とリズムなど、多くの生理活動に影響を与える。これらの現象はすべて宗気の盛衰と関係がある
7)。
③ 資先天(先天を助ける)
[詳細]
宗気は後天に生成された
気として、先天の気、つまり元気に対し重要な援助の働きを持つ。
以下のように先天の気(元気)と後天の気(宗気)は、
三焦を通路として相まり、一身の気となる。
o
元気は下から上へ運行し、
胸中に散布して、後天の宗気を助ける
o 宗気は上から下へと分布し、
臍下丹田に蓄積され、先天の気、つまり元気を助ける
このように、先天と
後天の気が相まって一身の気と成る。
父母より
稟受した
先天の精には量的な限りがあり、
化生される元気も同じように限りがある。したがって、一身の気の盛衰は、主に宗気の生成によって決まることとなる。宗気の生成は脾・肺の機能が正常であるか否か、飲食による栄養が充足しているか否かにより決定する。
それゆえ、一身の気の不足(いわゆる
気虚のこと)は、先天的には主に腎、後天的には主に脾肺に問題があると考えられる。
3) 営気 ( えいき / yíngqì / Nutrient Qi )
(1) 営気の概念
[定義] 後天の気の一つ。脈中を流れ全身を栄養する働きを持つ気。
[解説] 後天の気の一つ。水穀の精気の中で、特に豊かな栄養分を持った精華部分から化生した気である。化生すると同時に脈中に入り全身を巡る。営気には臓腑・経絡など全身の組織・器官が生理活動をする上で必要な栄養物質を含んでおり、全身を巡ることでこれらを栄養する。
[文献記載] 他文献の営気に関する定義など。
(2) 生成と分布
営気はの生成と分布は以下の通りである。
o 脾胃が運化した水穀の精微を来源とし
o 水穀の精より化生した水穀の気の精華な部分が、さらに化生され営気となる
o 脈中に入り全身を運行する
[詳細]
営気は水穀の精より
化生し、脈中に入り、休むことなく脈中を循り、内は臓腑、外は
肢節まで全身を運行する
8)。
(3) 生理機能
営気には以下二つの生理機能がある。
① 血の化生 [詳細]
営気は
津液と調和し、共に脈中に注ぎ
血と成り
9)、一定の血量を保持する。
② 全身の栄養
[詳細]
営気は血脈中を循り、五臓六腑・
四肢百骸など全身に流注しこれらを滋養する。営気は全身の臓腑・組織に必要な営養を提供しているため、生命活動において非常に重要な意義を持つ
10)。
営気の「血の化生」と「全身の栄養」の生理機能は相互に関連している。
営気の不足は、血虚及び全身の臓腑・組織の栄養不足のため、生理機能の減退を引き起こす。
4) 衛気 ( えき / wèiqì / Difencive Qi )
(1) 衛気の概念
[定義] 後天の気の一つで脈外・体表・臓腑などに分布し外邪の侵襲を防ぐなどの働きを持つ気。
[解説] 後天の気の一つ。水穀の精気の中で、剽悍(早くてすばやい)で滑利(滑らか)な部分から化生した気である。そのため活動性が高く動きが速いという性質があり、血脈中に拘束されることなく、外は皮膚・肌肉から、内は臓腑にいたるまでの体表・脈外にくまなく分布する。外邪の侵襲を防ぐほか、皮毛を潤沢に保ち、臓腑や筋肉・皮毛などを温め、腠理の開闔や汗の排出をコントロールし、体温を一定に保つ働きもがある。
[文献記載] 他文献の衛気に関する定義など。
(2) 生成と分布
衛気はの生成と分布は以下の通りである。
o 脾胃が運化した水穀の精微を来源とし
o 水穀の精より化生した水穀の気の剽悍(早くてすばやい)で滑利(滑らか)な部分が、さらに化生され衛気となる
o 脈外を運行する [詳細]
衛気は
水穀の
精より
化生し、脈外を運行し、脈道の拘束を受けず、外は皮膚肌腠、内は胸腹の臓腑まで全身に散布する。
(3) 生理機能
衛気には以下三つの生理機能がある。
① 外邪の防御 [詳細]
衛気は外邪の侵入を
防御する作用を備える。
衛気は
肌表に散布し、外邪に抵抗して体内への侵入を防ぐ防衛の働きをする
11)。
したがって、衛気が充実していれば肌表を護衛できるため、外邪の侵襲を受けにくい。
逆に衛気が虚弱ならば、外邪を感受しやすく、発病を繰り返す。
② 全身の温養 [詳細]
衛気は全身を
温煦する働きを持つ。
内は臓腑、外は
肌肉・
皮毛にいたるまで、全ての組織は衛気の
温養を受けている。これは、臓腑・
肌表などの正常な生理活動のための条件である。
衛気が充足すれば身体は温養され、体温を一定に維持できる。衛気が不足すると温煦は減弱し、虚に乗じて風寒湿などの
陰邪が肌表を侵襲して、寒性の病変が出現する。また、衛気が局部的な運動制限を受け鬱積すると熱が生じ、熱性の病変が出現する
12)。
③ 腠理の制御 [詳細]
衛気は
腠理の
開闔の制御・調節を通して、汗を規則的に排泄させている。
衛気のこの制御作用は、以下二つの働きを備える。
o
固摂作用
o
推動作用
身体は汗の正常な排泄を通じ、体温を一定に維持できる。これにより、体内・体外の環境間の協調と平衡を保持している
13)。したがって、衛気の虚弱は、腠理制御の機能の失調を引き起こし、無汗・多汗あるいは
自汗などが出現する。
上述①~③の機能の間には連携と協調の関係がある。
o 外邪の防御と腠理の制御の関係:
これらの機能の関係は大変密接である。もし腠理が緩み、汗が出て止まらなければ容易に邪気の侵襲を受ける。逆に腠理が緻密ならば、邪気は容易に侵入できない。
o 温養機能と腠理の開闔の関係:
これらの機能の関係は、体温の調節において密接な関係にある。体温を正常に保持するためには温煦による昇温と出汗による降温の絶え間ない協調が必要である。
温煦が強く出汗が足りなければ、身熱無汗の症状が出現する。反対に温煦が弱く出汗が多すぎれば、皮膚の冷え・多汗などの症状が出現する。
『霊枢・本蔵篇』14)には、これら衛気の三つの機能に対する概括の記載がある。
5)営気と衛気の関係
営気と衛気の間には共通点もあり相違点もある。以下にその例を挙げる。
(1) 共通点
営気・衛気はどちらも脾胃により化生された水穀の精微を来源とする。
(2) 相違点
① 性質
[詳細]
o
営気の性質は清純であり、栄養に富んでいる
o
衛気の性質は剽悍(早くてすばやい)で滑利(滑らか)であり、運動性が高い
② 分布
[詳細]
③ 機能
[詳細]
このように、営衛の二気には性質・分布・機能などに違いが見られる。
総じて言えば、営気は陰に属し、衛気は陽に属すといえる。 [詳細]
体内の陰陽には相互の協調が必要である。営衛の協調により正常な体温や汗の分泌などを維持し、また邪気に対する抵抗力や臓腑の生理活動を発揮できる。
営衛の二気の失調は、悪寒発熱・無汗あるいは多汗・「昼不精夜不瞑(昼間ぼんやりし、夜眠れない)」・風邪をひきやすい、などの病態を引き起こす。
1) 『難経・三十六難』"命門者、諸神精之所舎、原気之所繋也"(命門は諸々の神精の舎る所、原気の繋る所なり)
2) 『景岳全書・論脾胃』"故人之自生至老、凡先天之有不足者、但得後天培養之功、亦可居其強半、此脾胃之気所関于人生者不小。"(故に人の生まれより老に至るは、凡そ先天の不足が有り、後天の培養の力を得、則ち天の功を補い、亦其れ強半居なるべし、此脾胃の気の人の生に関する所小さからず。)
3) 『難経六十六難』"三焦者、原気之別使也、主通行三気、経歴於五蔵六府"(三焦は、原気の別使なり、三気を通行し、五蔵六府に経歴するを主る)
4) 『景岳全書・搏忠録下』"命門為元気之根、為水火之宅、五臓之陰気非此不能滋、五臓之陽気非此不能発。"(命門は元気の根を為し、水火の宅と為す。五臓の陰気は、滋すること能わざるにあらず。五臓の陽気は、発すること能わざるにあらず。)
5) 『霊枢・邪客篇』"宗気積于胸中、出于喉?(口龍)、以貫心脈、而行呼吸焉。"(宗気は胸中に積み、喉?(口龍)に出て、以って心脉を貫き、而して呼吸を行なう。)
6) 『素問・平人気象論篇』"胃之大絡、名曰虚里、貫鬲絡肺、出於左乳下。其動応衣(手)、脈宗気也。"(胃の大絡は、名づけて虚里と曰う。鬲を貫き肺を絡(まと)い,左の乳の下に出ず。其の動 衣に応ずるは、脈の宗気なり。)
7) 『讀医随筆・気血精神論』"宗気者、動気也。凡呼吸・語言・声音、以及肢体運動、筋力強弱者、宗気之功用也。"(宗気なる者は、動気なり。凡そ呼吸・言語・声音、乃ち肢体運動を以つ、筋力の強弱は、宗気の功用なり。)
8) 『素問・痺論』"衛気者、所以温分肉、充皮膚、肥腠理、司関闔者也"(衛気なる者は、分肉を温め、皮膚を充たし、腠理を肥やし、関闔を司るゆえんの者なり)
9) 『霊枢・邪客篇』"営気者、泌其津液、注之於脈、化以為血"(営気なる者は、其の津液を泌し、これを脈に注ぎ、化して以て血と為し)
10) 『霊枢・営衛生会篇』"此所受気者、泌糟粕、蒸津液、化其精微、上注于肺脈、及化而為血、以奉生身。莫貴于此、故独得行于経隧、命曰営気。"(此の受くる所の気は、糟粕を泌し、津液を蒸し、其の精微を化し、上りて肺脈に注ぎ、乃ち化して血と為し、以って身を奉生す。此れより貴きはなし、故に独り経隧を行くことを得、命づけて営気と曰う。)
11) 『素問・痺論篇』"衛者、水穀之悍気也。其気慄疾滑利、不能入於脈也。故循皮膚之中、分肉之間、訓熏於肓膜、散於胸腹"(衛なる者は、水穀の悍気なり。其の気 慄疾滑利にして、脈に入ること能わざるなり。故に皮膚の中、分肉の問に循いて、肓膜を熏じ、胸腹に散ず)
12) 『讀医随筆・気血精神論』"衛気者、熱気也。凡肌肉之所以能温、水穀之所以能化者、衛気之功用也。虚則病寒、実則病熱。"(衛気は、熱気なり。凡そ肌肉をもって温むる能う所の、水穀を化す能うところの者、衛気の功用なり。虚すれば則ち寒を病み、実すれば則ち熱を病む。)
13) 『景岳全書・雑証漠』"汗発于陰而出于陽。此其根本則由陰中之営気、而其啓閉則由陽中之衛気。"(汗は陰より発し陽に出づ。此れその根本は則ち陰中の営気にあり、その啓閉は則ち陽中の衛気にあり。)
14) 『霊枢・本蔵篇』"衛気者、所以温分肉、充皮膚、肥腠理、司関闔者也"(衛気なる者は、分肉を温め、皮膚を充たし、腠理を肥やし、関闔を司るゆえんの者なり)
6. その他の気
中医学において人体の気は、上記「5. 気の分類」で紹介したもの意外にも様々な名称の気がある。以下に主なものを紹介する。
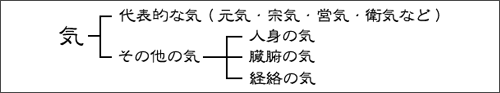
1) 人身の気
人身の気とは、すなわち全身の気のことである。「人気」あるいは「気」と呼ばれる。 [詳細]
人身の気は、人体のあらゆる臓腑・組織を構成し、全身を運行する極めて細かな
精微物質である。
人身の気は、以下の三者が融合し生成される。
o
先天の精より
化生した
気
o 水穀の精より化生した気
o 吸入した自然界の
清気
人身の気は、以下の働きにより人体の生命過程を維持している。
o 臓腑・経絡・形体・官竅などの生理活動を推動・制御する
o 血・津液・精の運行・輸布・代謝を推動・制御する
また、人身の気は全身に分布する。
分布する部位により、特有の運動形式や機能が、それぞれに異なる名称が付けられている。以下に例を挙げる。
o 人身の気は邪気に対し「正気」と呼ばれ、防御・抗邪調節・快復などの作用を備える。
o 生成の来源から、先天の精より化生したものを「元気」、水穀の精より化生したものを「穀気」と呼ぶ。
o 分布部位の違いから、脈中を行くものを「営気」、脈外を行くものを「衛気」、穀気と自然界の清気が胸中に聚ったものを「宗気」、臓腑に分布するものを「臓腑の気」、経絡に分布するものを「経絡の気」と呼ぶ。
2) 臓腑の気、経絡の気
臓腑の気・経絡の気は人身の気の一部である。
人身の気は臓腑・経絡へ分布し、それぞれの臓腑・経絡の気となる。
これらの気は臓腑・経絡の構成・生理活動を推動・維持するための物質的な基礎である。 [詳細]
臓腑の気・経絡の気も
来源は
先天の精・水穀の精・自然界の
清気である。
臓腑の気は臓腑の精に由来する。その臓腑の精は先天の精と
後天の精が臓腑中に
聚まり生成されたものである。
臓腑の気は
元気・
宗気など代表的な
気とくくりは違うが、臓腑の気には元気・穀気・自然界の清気の成分が含まれている。
臓腑の気・経絡の気は、分布する臓腑・経絡によりそれぞれ構成成分や発揮する機能が異なっている。臓腑の気・経絡の気の活力は大変強く、その絶え間ない運動は臓腑・経絡の生理機能の動力を
推動・制御し、協調しあえる状態にしている。
中医学の「気」という名詞には、上述の他にもまだ以下の様な含意がいくつかあるので注意が必要である。 [詳細]
o 「邪気」:病を引き起こす素因
o 「水気」:体内の正常でない水液
o 「四気」:中薬における四種の性質
o 「六気」:自然界の六種の気候変化
これらの
気の含意は、ここで述べてきた人体の気と概念上はっきりとした区別がある。
7. 血・津液・精・神との関係
7.1.気と血の関係
気と血の間には"気為血帥(気は血の帥)"及び "血為気母(血は気の母)"と呼ばれる密切な関係が存在する。
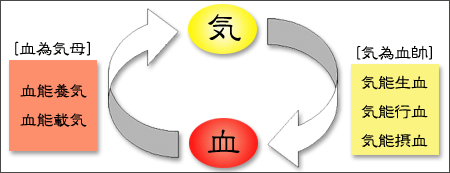
1) 気為血帥 (気は血の帥)
「気為血帥」には「気能生血」「気能行血」「気能摂血」の三つの意義が含まれる。
(1) 気能生血
「気能生血」とは気が血の化生(化血)を行う動力であることを指している。ここでいう気とは血の化生に関係する臓腑の気の推動作用や発奮作用を指す。 [詳細]
気が
血を
化生する過程は以下の二段階からなる。
o 物質基礎である
営気・
津液・
腎精の生成
o 物質基礎から血への
転化
気が充実していれば血の化生(化血)はスムーズに行われ、血は十分に生成され、その機能は充実する。一方、気が不足すれば化血の機能は減退し、血虚を引き起こしやすくなる。
臨床上、血虚を治療する際、気能生血の理論に基づき、しばしば補血剤に補気薬を配合し優れた効果を獲得している。
(2) 気能行血
「気能行血」とは血の運行に気の推動作用が不可欠であることを指している。 [詳細]
気の
推動作用には主に
o 肺の
宣発・
粛降作用
o 心の主血脈
o 肝の
疏泄
などの働きが大きく関わっている
1)。そのため、これら臓腑の気の状態が
血の運行を左右する。
例えば、以下に示すように、気の推動作用が失調すると
瘀血が生じることがある。
o 「
気虚」により血の
推動が無力となった場合
o 「
気機鬱滞」により血に対する推動が滞った場合
また、
気機(昇降出入)の失調は血の運行にも影響する。
o 「気逆」により血は気につられ上昇する
o 「気陥」により血は気に従い下降する
したがって、臨床で血行の失調を治療する際、補気・
行気・
降気・
昇提の薬物を配合することが多い。これは気能行血の理論を応用した実践例である。
(3) 気能摂血
「気能摂血」とは血が脈中を循環するために気の固摂作用が必要であることを指す。 [詳細]
血に対する
気の
固摂作用のなかで、脾の
統血作用はとりわけ重要な意義を持つ。脾気の状態がこの統血作用を大きく左右する。
脾気が充実していれば統血作用は十分に働き、
血は脈外に漏れることなく循行する
脾気虚弱により統血作用が低下すると、血は脈中に留まることができず各種の出血を生じる。(「気不摂血」「脾不統血」と呼ばれる)
したがって、「気不摂血」「脾不統血」などの出血病変を治療する際には、必ず「健脾補気」の方法を用い、
益気により統血(摂血)させなければならない。また、臨床では大出血によるショックが発生した場合、この理論に基づき大量の輸血と同時に
補気薬を用いる。
2) 血為気之母(血は気の母)
「血為気之母」には、「血能養気」と「血能載気」の二つが含まれる。
(1) 血能養気
「血能養気」とは、気が充実しその機能を発揮するためには血の絶え間ない栄養提供が必要であることを指す。 [詳細]
血の栄養提供は、以下二点のために行われる。
o
気の生成
o 気の機能活動の発揮
これが血の
濡養作用の目的であり、血が充実することで気の活動は盛んになる。
臓腑・四肢関節・
官竅などの部位が血からの栄養提供を失えば、次のような病変が生じる。
o 気の不足
o 気の機能の喪失による病変
血虚の患者がしばしば
気虚の病証を合わせ持つのは、この「血能養気」の法則に準じている。
(2) 血能載気
「血能載気」とは気が血中に存在することで体外に散出せず、全身を運行できることを指す2)3)。
[詳細]
大出血を起こした病人は
血と同時に
気も大量に喪失し「渙散不収」(血が不足し気が散逸し収まらない状態)から、さらに「気髄血脱」(気が浮いて漂うような気脱病変)を引き起こすことがある。
「血為気之母」とは血の気に対する基礎的な作用である「血能養気」と「血能載気」を総括した表現である。
血は陰に属し、気は陽に属す。生命活動はこの陰陽間の平衡と協調により正常に行われる。したがって気と血を調え陰陽の平衡を調えることは疾病の治療によく用いられる常用の治療法則である4)。
7.2.気と津液の関係
気と津液の関係は、気と血の関係に類似している。
津液の生成・輸布と排泄は気の昇降出入と気化・温煦・推動及び固摂作用に頼っている。
気の体内での存在は、血だけではなく、津液にも依存している。ゆえに津液も気の担体といえる。
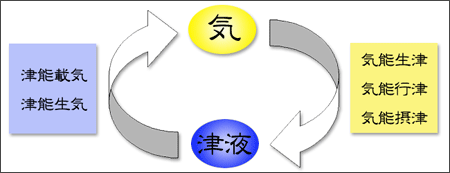
1) 気能生津
気は津液生成の原動力であり、津液の生成は気の推動作用に頼っている。 [詳細]
津液は飲食により摂取した
水穀に由来し、水穀は脾胃の
運化・小腸の分別清濁・大腸の主津など一連の臓腑の生理活動を経て、
精微な液体部分が吸収され、津液に
化生し全身に輸布される。
津液生成の一連の
気化過程では、多くの臓腑の気、特に脾胃の気が極めて重要な働きを果たす。
脾胃など臓腑の気が充実すると、津液を化生する力が増し、津液は充足する。
脾胃など臓腑の気が不足すると、津液を化生する力は弱まり、津液不足を引き起こす。このことから、津液不足の治療時には補気生津の法則を用いることが多い。
2) 気能行津
気は津液の正常な輸布・運行の原動力である。津液の輸布・排泄などの代謝活動から、気の推動作用と昇降出入の運動は切り離せない。 [詳細]
津液は脾胃により
化生され、脾・肺・腎及び
三焦の
気の昇降出入の運動を経て、
推動され全身へ輸布される。その後、代謝過程で生じた廃液と余剰な水分は汗・尿あるいは水蒸気に
転化され体外へ排出される。津液の輸布・転化および排泄の一連の過程は
気化を通じて行われる。
気虚により
推動作用が減弱すると、気化は無力となり、また
気機鬱滞ならば
気化は妨げられる(「気不行水」と呼ばれる)。これらの病態は津液の輸布・排泄障害を引き起こし、
痰・飲・水・湿など病理産物を形成する。
臨床では、痰・飲・水・湿などの病理産物と、それらが引き起こす影響を取り除くため、利水湿・化
痰飲の方法と補気・
行気法を同時に用いることが多い。これは気能行津の理論を応用した具体例である。
3) 気能摂津
気の固摂作用は津液の不要な流出を防いでいる。
また、気は津液排泄に対し節度ある制御をし体内津液量を一定に維持している。 [詳細]
例えば、
衛気は
腠理の
開闔を司り、肌腠を
固摂し、津液を過多に
外泄させない。これは津液に対する
固摂作用の現れである。
気の不足により固摂の力が減弱すれば、多汗・自汗・多尿・遺尿・小便の失禁など多くの病理現象が出現する。臨床では、補気法を用い津液の過多の外泄を抑える方法を用いることが多い。
4) 津能載気
津液は気運行の担体の一つである。[詳細]
血脈中以外での
気の運行は
津液に頼っている。気は津液がなければ、漂い離散し帰るところがない。津液中には気が含まれるため、津液の消耗は同時に気の損傷を招く。
例えば暑熱病証では、津液の消耗だけではなく、汗とともに気も
外泄するので、少気懶言・倦怠感・無力感など
気虚の症状が現れる。大汗・
大吐・
大瀉など津液の大量の消耗時には、気も津液にしたがい大量に
外脱する。このような病態を「気随津脱」と呼ぶ。出汗・嘔吐・下痢などは津液の消耗と同時に、気も損傷する
5)。そのため、臨床で汗法・吐法と下法を使用する際には注意が必要で、病が治ればすぐに服用を止め、過多の使用により変証を招かないようにする。
津液は気の担体であるため、気は津液に頼り運行する。
津液の輸布・代謝が正常であれば、
気機も伸びやかである。このような関係を「津行則気行(津行けば則ち気行く)」と呼ぶ。逆に、津液の輸布・運行が障害を受けると、気機の
鬱滞・
不暢を引き起こすことが多い。このような病態を「津停則気滞(津停まれば則ち気滞る)」と呼ぶ。「津停則気滞」と前述の「2) 気能行津」で述べた「気不行水」の病理変化は互いに因果関係にある。両者は影響しあい、悪循環を形成し、病情も悪化することが多い。そのため、臨床では治療効果を高めるために、利水薬と行気薬を同時に使用することが多い。
5) 津能生気
水穀から化生される津液は、脾の昇清を通じ肺に上輸され、さらに肺の宣降・通調水道により腎と膀胱に下輸する。津液はこれらの輸布の過程において、各臓腑の陽気が持つ蒸騰・温化の作用により気化される。 [詳細]
臓腑・組織・
形体・
官竅に散布し、生理活動を促進している。そのため、津液不足により気の減少を引き起こすことがある。
7.3.精・気・神の関係
精・気・神三者の間には相互に依存し利用し合う関係がある。
精は気を化生し、気は精を生むように、精と気の間には相互に化生しあう関係がある。
精気は神を生じ、精気は神を養う。精と気は神の物質基礎であり、また神は精と気を統御する。
したがって、精・気・神の三者は切っても切り離すことができないため人身「三宝」と呼ばれる。
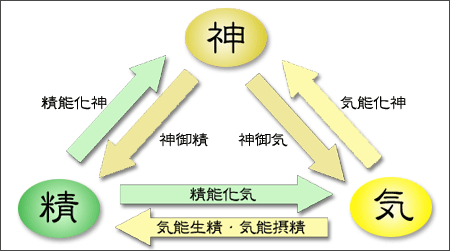
1) 気能生精摂精
気の絶えることのない運行は精の化生を促進している。腎中に蔵される精は、先天の精を基礎とし、後天・水穀の精の絶え間ない充養に頼り始めて充実し盛んとなる。 [詳細]
臓腑の気が充足し機能も正常であって、はじめて水穀の精を
運化・吸収することができ、五臓六腑の精は満ちあふれ、腎に流れ込み蔵される。このことから、
精の
化生は気の状態により左右されることが分かる。
気は精の化生を促進するだけではなく、精を
固摂している。固摂されることで精は
聚まり充実し、むやみに
外泄し損傷することを防いでいる。これは気の
固摂作用によるものである。
これらのことから、
気虚は精の生成不足あるいは精を
固聚できないため
精虧・
失精などの病証を招く。これらに対し臨床では、
補気生精・
補気固精などの治療方法を用いることが多い。
2) 精能化気
人体の精は、気の推動作用により気へと化生することができる。 [詳細]
各臓の精は各臓の気を
化生し、腎中に蔵される
先天の精は
元気へ、水穀の精は穀気へと化す。
精は
気化生の根源であり、精が充足していれば気は充実し満ちあふれ、各臓腑経絡に分布し、各臓腑経絡の気も充足する。
各臓の精が充足していれば各臓の気も充実し、各臓腑・
形体・
官竅の生理活動を
推動することができる。
したがって、精が充実すれば気は旺盛になり、精が不足すれば気も衰える。臨床において精虚及び
失精の患者に
気虚の病理表現が多く見られる。
3) 精気化神
精と気は神化生のための物質基礎であり、神は精と気の滋養を受けることではじめて正常に作用を発揮することができる。 [詳細]
精が満ちれば
神は明瞭となり、精が不足すれば神は疲弊する。
気が充実すれば神は明瞭となり、気が虚すれば神は衰える。そのため気は「神の母」と呼ばれる。
神は生命活動の主宰であり、精と気、そして
血や
津液などを含めこれらは全て神の物質基礎である。神と形体は対・相互依存の関係にあり、これら人体の基本物質は人の
形体に属す。
神は形体に宿り、形体を離れた神は存在することができない。
4) 神御精気
神は精気を物質基礎とし、逆に神は気や精を統御する6)。 [詳細]
臓腑・
形体・
官竅の機能活動及び
精・
気・
血など物質の新陳代謝は、すべて
神の統御を受けている。
形(形体)は神の住みかであるが、神は形(形体)の主である。神が安定していれば精は
固摂され気は通暢である。神が揺れ動き不安定であれば精は失われ気は衰える。
精・気と神の間には対立・統一の関係がある。
中医学の形神統一観は養生と予防及び診断治療・病勢の推測の重要な理論根拠である7)。
1) 『血証論・陰陽水火気血論』"運血者、即是気。"(血を運ぶ者は、即ちこれ気なり。)
2) 『血証論・吐血』"血為気之守。"(血は気の守を為す。)
3) 『張氏医通・諸血門』"気不得血、則散而無統。"(気は血を得ざれば、則ち散じて統無し。)
4) 『素問・調経論篇』"血気不和、百病乃変化而生"(血気 和せざれば、百病 乃ち変化して生ず)
5) 『金匱要略心展・痰飲』"吐下之余、定無完気"(吐下の余、宗気無しと定む。)
6) 『理虚元鑑』"夫心主血而蔵神者也、腎主志而蔵精者也。以先天生成之体質論、則精生気、気生神;以后天運用之主宰論、則神役気、気役精。"(夫れ心は血を主りて神を蔵する者なり、腎は志を主りて精を蔵する者なり。以て先天の体質を論ずるは、則ち精は気を生じ、気は神を生ず;以て後天の運用の主宰を論じれば、則ち神は気を役し、気は精を役す。)
7) 『素問・上古天真論篇』"故能形与神倶、而尽終其天年"(故に能く形と神と倶にして、尽く其の天年を終え)、"独立守神、肌肉若一。故能寿敝天地、無有終時"(独立して神を守り、肌肉一の若し。故に能く寿は天地を敝し、終る時あることなし)